| ホーム > 京都の世界文化遺産一覧 > 延暦寺 > 延暦寺横川地区 |
| ホーム > 京都の世界文化遺産一覧 > 延暦寺 > 延暦寺横川地区 |
|
延暦寺について 比叡山延暦寺は天台宗の総本山であり、比叡山頂から東側斜面にかけて、三塔十六谷三千坊と言われるほどの大寺である。三塔とは「東塔(とうどう)」、「西塔(さいとう)」、「横川(よかわ)」の各エリアを指している。 |
延暦寺・横川地区へのアクセス |
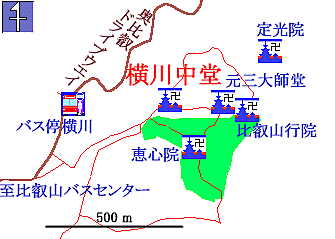 JR湖西線「比叡山坂本」駅下車。 駅から比叡山・東塔地区までは「延暦寺・東塔地区のページ、アクセスの項」参照。 東塔地区にある「延暦寺バスセンター」から「横川(よかわ)」行きの比叡山内シャトルバスに乗車し終点の「横川(よかわ)」で下車する。乗車時間約13分。 西塔地区からは「西塔(さいとう)」より「横川(よかわ)」行き比叡山内シャトルバスに乗り「横川(よかわ)」で下車する。所要時間約10分。 比叡山内シャトルバス「横川」行きは「延暦寺バスセンター」発10:06から16:36まで30分毎に運行されているが、運行期間は3月20日〜11月30日及び1月1日〜1月3日であり、冬期(1月1日〜1月3日を除く)は運休している。 冬期は自家用車かタクシーを利用する以外、東塔地区より徒歩による外はないが1.5〜2時間を要するものと思われる。 |
延暦寺の縁起、歴史 |
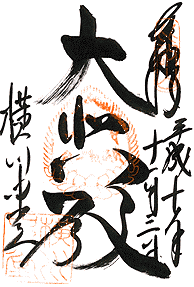 |
近江国分寺で得度し奈良東大寺の戒壇院で具足戒を受けた最澄上人が、理想の布教地を比叡山に求め、延暦7年(788年)に山上に庵を結び、自ら刻んだ薬師如来像を本尊として安置し、「一乗止観院」と称したのが延暦寺の創始であると伝えられている。 桓武天皇の平安遷都に伴い、御所の鬼門の方向にある最澄上人の草堂が国家を鎮護するための官寺に選ばれ、最澄上人は天皇のための侍僧の一人に加えられたという。 最澄上人は延暦23年(804年)に唐に渡り、翌年に帰国する。帰国後、天台宗を開き「一乗止観院」を「根本中堂」に改称したとされている。この頃から、高野山を開いた空海との間に確執が生じ始めたようである。 |
現在の寺名「延暦寺」に改名されたのは、最澄上人没後の弘仁14年(823年)であるとされている。その後、他山の僧兵との争い等で、しばしば多くの堂を焼失したが、その度に復興されてきたようである。 最澄上人のあと、比叡山から数多くの名僧、高僧を輩出しており、法然、親鸞、道元、日蓮など著名な僧もすべてここで修行したといわれている。最澄上人と対立していた空海のもとからは高名な僧が殆ど輩出していないのと比べ対照的である。 元亀2年(1571年)には織田信長の軍勢によって比叡山全山すべて焼き払われた。建物で残ったのは西塔にある瑠璃堂のみといわれており、僧侶、それに坂本の町から逃げてきた一般の人合わせて二千人以上の人々が焼殺、惨殺されたという。その後、秀吉、家康によって寺は復興された。しかし、その傷跡は実に大きかったようで、信長に対する恨みは、1994年の法要で表面的には一応解消したことになっているが、今でも比叡山は神秘的で怖いというイメージは残っているようで、このイメージは将来にわたっても消え去ることはないであろうといわれている。 |
横川中堂 |
 |
「横川」バス停から参道を東に進むと、最初に目に付く大きな建造物は、石垣の上に建っている朱塗りも鮮やかな舞台造りの「横川(よかわ)中堂」(左及び直下の写真)であり、横川地区の中心となる堂である。 横川は最澄上人の教えに従って、慈覚大師円仁が開いたといわれる場所である。 |
その円仁が嘉祥元年(848年)に根本観音堂として創建したとされるのが横川中堂である。 |
 |
他の堂宇と同様、元亀2年(1571年)、織田信長による比叡山の焼き討ちにより、横川中堂も全焼したようであるが、後、豊臣秀頼により再建されたといわれている。その後、昭和17年(1942年)に落雷により焼失、現存の堂は昭和46年(1971年)に建造されたものという。それだけに堂の外観は新しく、朱色の塗装も鮮やかであり、歴史のある寺としては何となく違和感がある。 |
「横川中堂」の本尊「木造聖観音立像」は不思議なことに度重なる火災の難を免れているというが、その表情は柔和で多くの苦難を経ているようには思えない。 本尊「木造聖観音立像」は平安時代の作といわれており、重要文化財に指定されている。 |
根本如法塔 |
 |
「横川中堂」の西北側、参道から細い坂道を登ったところの木立の中に朱塗りの二重の塔、「根本如法塔」(左の写真)が見える。 横川を開いた慈覚大師円仁が天長年間(824-832年)に法華経を書写し、これを如法堂に安置したとされている。以後、如法堂が横川における信仰の中心になったようである。 大正12年(1923年)、如法堂跡に塔を建てるための工事中に経箱が発掘されたという。銅製の箱に金メッキが施され、蓋には「妙法蓮華経」と書かれており、この箱は後に「金銅経箱」として国宝に指定された。 現存の「根本如法塔」は大正14年(1925年)に建立されたようである。 |
元三大師堂 |
 |
「横川中堂」の前の参道を東の方向に進むと「元三(がんざん)大師堂」(左の写真)に着く。 ここは天台宗中興の祖とされている慈恵大師良源(元三大師)の住居の跡を継いでいるといわれている場所である。 |
康保4年(967年)から村上天皇の命により、ここで法華経の論議法要が春夏秋冬に行われたので、「四季講堂」ともよばれている。 |
 |
左の写真は「元三大師堂」の「本堂」であり、本尊として元三大師の画像が祀られている。 また、ここはおみくじ発祥の寺といわれている。今でも、先ず僧侶の前で自分の悩み事を話し、おみくじを授受する。次いでそのおみくじに書いてある内容について10分程度僧侶から教えを受けなければならない。それだけにおみくじ代は高価である。 |
「元三大師堂」は滋賀県文化財に指定されている。 |
恵心院 |
 |
「元三大師堂」の前から南の方向へ数分歩いたところに「恵心院」(左の写真)がある。 ここは恵心僧都の旧跡といわれ、恵心僧都はここに籠もり仏堂修行と著述に専念し、浄土教の基礎を築いたとされている。 「恵心堂」は横川中堂や何となく明るい感じのする元三大師堂から離れた場所にあり、暗い感じがする小堂であるが落ち着いて修行ができる雰囲気に囲まれている。 |
比叡山行院 |
 |
「元三大師堂」から東側に歩いて2〜3分のところに「比叡山行院」(左の写真)がある。 ここは天台宗の修行道場であり、読経の声が地の底からわき上がるように荘厳に響き渡っている。この付近は観光客も少なく静寂であり、修行道場は周辺の環境によくとけ込んでいる。 |
定光院 |
 |
「比叡山行院」の前から東北方向に坂を15分程度歩いて下ると「定光院」(左の写真)に行き着く。 「定光院」は日蓮上人の旧跡であるといわれており、境内には日蓮上人の銅像が立っている。 |
銅像とその横に建っている建物はどう見ても俗っぽい。これらは由緒ある比叡山でも特に山奥にあり、観光客の訪れることの少ないこの寺にそぐわないように感じられてならない。 |
その他コメント 横川地区は東塔地区よりかなり離れた場所にある関係からか観光客はそう多くはなく、東塔地区に比べ静かである。ただ、雰囲気から見れば西塔地区よりも観光地化する要素があるように思われる。東塔地区は明るく派手、西塔地区は落ち着いており荘厳、横川地区は静かなところは西塔地区に似ているが、荘厳さは西塔地区に及ばないのではなかろうか。 |
| 京都の世界文化遺産一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
| 延暦寺・東塔地区のページ | 延暦寺・西塔地区のページ |
Yukiyoshi Morimoto