| ホーム > 京都の世界文化遺産一覧 > 延暦寺 > 延暦寺東塔地区 |
| ホーム > 京都の世界文化遺産一覧 > 延暦寺 > 延暦寺東塔地区 |
| 延暦寺について 比叡山延暦寺は天台宗の総本山であり、比叡山頂から東側斜面にかけて、三塔十六谷三千坊と言われるほどの大寺である。三塔とは「東塔(とうどう)」、「西塔(さいとう)」、「横川(よかわ)」の各エリアを指している。 |
延暦寺・東塔地区へのアクセス |
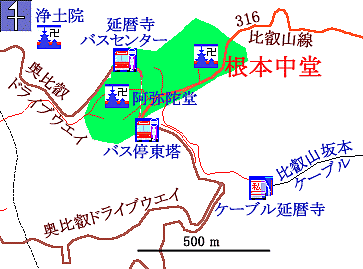 JR湖西線「比叡山坂本」駅下車。駅前からバスが下記の発車時刻表の通り3系統出ているが、9月、10月の日曜祝日及び11月の土日曜祝日を除き運転頻度は少ないので歩いた方が便利である。 JR「比叡山坂本」駅下車。湖西道路の高架下をくぐり西の方向に進む。日吉大社の前を南の方向に曲がり約200m進むと右手に比叡山高校があるので、その下を西の方向に進むと「ケーブル坂本」駅に着く。JR「比叡山坂本」駅から「ケーブル坂本」駅まで徒歩25〜30分。 ケーブルで終点「ケーブル延暦寺」まで上がり(乗車時間約11分)、北西の方向に道なりに進むと徒歩約10分で比叡山東塔地区に着く。 JR「比叡山坂本」駅前からバス発車時刻は次の通り(2001年11月現在)。 |
| 時 | 「石山駅」行 (京阪バス) 「坂本ケーブル乗場」 で下車(a) |
「西教寺」行 (江若バス) 「日吉大社前」 で下車(b) |
「ケーブル坂本駅」行* (江若バス) 「ケーブル坂本駅」 で下車(c) |
| 8 | -- | 22 [48] {49} | -- |
| 9 | -- | 38 | -- |
| 10 | 39 | 15 | 06 36 |
| 11 | 39 | 00 53 | 06 38 |
| 12 | 39 | -- | 06 |
| 13 | 39 | 05 | 04 28 |
| 14 | 39 | 05 | 04 28 |
| 15 | 39 | 05 52 | 04 28 |
| 16 | 39 | 52 | 04 28 |
| (注) [48]:平日運転 {49}:土曜、日曜、祝日運転 *:9月、10月の日曜、祝日及び11月の土曜、日曜、祝日運転 |
| (a):西の方向へ比叡山高校の下を徒歩2〜3分で「ケーブル坂本」駅に着く。 (b):日吉大社の前を南の方向に曲がり、約200m進み右手に見える比叡山高校の下を西の方に進むと「ケーブル坂本」駅に着く。 (c):バスは「ケーブル坂本」駅前に着く。 |
延暦寺の縁起、歴史 |
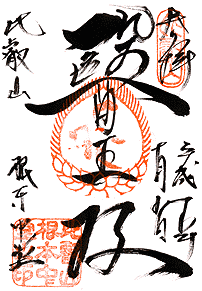 |
近江国分寺で得度し奈良東大寺の戒壇院で具足戒を受けた最澄上人が、理想の布教地を比叡山に求め、延暦7年(788年)に山上に庵を結び、自ら刻んだ薬師如来像を本尊として安置し、「一乗止観院」と称したのが延暦寺の創始であると伝えられている。 桓武天皇の平安遷都に伴い、御所の鬼門の方向にある最澄上人の草堂が国家を鎮護するための官寺に選ばれ、最澄上人は天皇のための侍僧の一人に加えられたという。 最澄上人は延暦23年(804年)に唐に渡り、翌年に帰国する。帰国後、天台宗を開き「一乗止観院」を「根本中堂」に改称したとされている。この頃から、高野山を開いた空海との間に確執が生じ始めたようである。 |
現在の寺名「延暦寺」に改名されたのは、最澄上人没後の弘仁14年(823年)であるとされている。その後、他山の僧兵との争い等で、しばしば多くの堂を焼失したが、その度に復興されてきたようである。 最澄上人のあと、比叡山から数多くの名僧、高僧を輩出しており、法然、親鸞、道元、日蓮など著名な僧もすべてここで修行したといわれている。最澄上人と対立していた空海のもとからは高名な僧が殆ど輩出していないのと比べ対照的である。 元亀2年(1571年)には織田信長の軍勢によって比叡山全山すべて焼き払われた。建物で残ったのは西塔にある瑠璃堂のみといわれており、僧侶、それに坂本の町から逃げてきた一般の人合わせて二千人以上の人々が焼殺、惨殺されたという。その後、秀吉、家康によって寺は復興された。しかし、その傷跡は実に大きかったようで、信長に対する恨みは、1994年の法要で表面的には一応解消したことになっているが、今でも比叡山は神秘的で怖いというイメージは残っているようで、このイメージは将来にわたっても消え去ることはないであろうといわれている。 |
根本中堂 |
 |
東塔地区における中心的な建物は延暦寺の総本堂にあたる「根本中堂」である(左及び直下の写真)。 現存する建物は寛永17年(1640年)に建造されたものといわれ、最澄上人の時代から数えて八代目の建物になるらしい。「根本中堂」は日本で三番目に大きい木造建築であるといわれている通り、その規模の大きさに驚かされる。 |
 |
内陣須彌壇の上、中央の厨子内に最澄上人の作とされている本尊の薬師如来が安置されているといわれているが、秘仏であり直接の拝観はできない。尤も内陣は非常に暗く、仮に厨子が開扉されていたとしてもその内部を見ることは不可能であろう。 内陣は外陣や中陣より低い位置にあり、石敷きの土間である。参拝者が入ることのできるのは中陣までである。 |
「根本中堂」は国宝に指定されている。 |
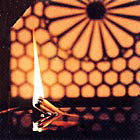 |
本尊の前には菊の紋章の描かれている六角形の三個の釣灯籠があり、菜種油が燃焼するほのかな光を放っている。これが延暦寺創始以来1200年間消えたことがないという「不滅の法灯」(左のコピー:JRの比叡山観光パンフレットより)である。法灯は周囲の暗さのなかで実に神秘的な雰囲気を醸し出している。中陣正面横に座っているとこの雰囲気に引き込まれのは私だけではないであろう。 |
但し、厳密に言えば、「不滅の法灯」が1200年間消えたことがないというのは正しくない。というのは上述したように約430年前、信長の軍勢により根本中堂も焼き払われており、この時に「不滅の法灯」も当然消えている。山形の立石寺(山寺)には根本中堂から分灯されていた「法灯」があり、この灯を持ってくることにより「不滅の法灯」を継続させたという。 |
文殊楼 |
 |
根本中堂正面の急な石段を上がったところ、根本中堂から見て東側に、「文殊楼」(左の写真)が建っている。この「文殊楼」は比叡山の総門の役もしているという。 ここには中国五台山の霊石が埋められているといわれている。急勾配の階段を上がった楼上には文殊菩薩が祀られているが、内部は雑然としており、何となく埃っぽい。 |
大講堂 |
 |
根本中堂の西側に「大講堂」(左の写真)が建っている。ここは僧侶の学問修行のための道場とされている。 以前の大講堂は昭和31年(1956年)に焼失し、その後、山麓にあった讃仏堂を移築したのが現存の建物であるといわれ、朱塗りも鮮やかで見た目にも新しい建物である。 |
「大講堂」の本尊は大日如来であり、脇には聖徳太子、桓武天皇をはじめ、法然、親鸞、道元、日蓮など、一宗の祖師の木像が安置されている。 「大講堂」は重要文化財に指定されている。 |
戒壇院 |
 |
大講堂の西側、一寸した高台の上に「戒壇院」(左の写真)が建っている。 ここは、天台宗の僧が住職になるための必修の条件である大乗戒(規律)を受ける堂で、年に一度授戒会が行われる。このためか「戒壇院」比叡山中でも最も重要な堂の一つであるとされている。 |
最澄上人が大乗戒壇院を建立すべく心血を注いでいたが、存命中は実現せず、最澄の死後7日目に嵯峨天皇より勅許が下ろされ、堂は天長5年(828年)に第一世義真座主により創建されたといわれている。 「戒壇院」は重要文化財に指定されている。 |
阿弥陀堂 |
 |
戒壇院の西側、広い石段を上がると広場の奥正面に、平安時代の建築様式をモデルとした「阿弥陀堂」(左の写真)が見える。 「阿弥陀堂」は昭和12年(1937年)に建てられたとされている。ここは滅罪回向の道場であり、全国壇信徒各家の先祖を祀っている。 |
法華等持院 |
 |
「阿弥陀堂」の西側に「法華等持院」がある。「法華等持院」は「東塔」(左の写真)、東塔の更に西側にある「潅頂堂」、「寂光堂」などから構成されている。 「法華等持院」は天台密教の根本道場として貞観4年(862年)に創建されたようであるが、信長の軍勢により焼き払われたのは他の堂宇と同様である。 「東塔」などは、信長の焼き討ちから400年ぶり、昭和52年(1977年)に再建された。「東塔」は根本中堂とともに重要な信仰道場になっているようである。 |
「阿弥陀堂」及び「法華等持院」の「東塔」は鮮やかな朱色に塗られており、建造されてから日時の経過も浅いこともあり、派手に見える。延暦寺の他の堂宇とくらべ若干異質の感じがしないでもない。 山王院 |
 |
戒壇院横の道を西塔の方へ進と奥比叡ドライブウエイの上にかかっている陸橋があり、これを渡ると木立の中に「山王院」(左の写真)が見える。 ここは、第六祖智証大師圓珍の住居であったとされている堂で、千手観音像を祀っているので千手院とも呼ばれている。他の堂宇から離れ孤立して建っており、古色蒼然とした裏寂しい感じのする堂である。 |
浄土院 |
 |
山王院横の杉木立の間の参道を下ると「浄土院」(左の写真)の前に出る。 浄土院は最澄上人(伝教大師)の御廟(墓)のある場所であり、周囲は非常に静寂で、ここは比叡山第一の浄域とされている。 左の写真中央に見えているのが浄土院の山門であり、その奥の建物が「浄土院拝殿」である。 |
 |
左の写真は「浄土院拝殿」である。通常、浄土院の山門は閉じられており、拝殿の前に出るには山門の左手にある小さな通用門をくぐって塀の中に入る。 「浄土院拝殿」の奥に「浄土院御廟」があり、弘仁13年(822年)に山内の中道院で56年の生涯を終えた最澄上人(伝教大師)の遺骸が奉安されているという。 |
直下の写真は正面から見た「浄土院御廟」である。 |
 |
浄土院で御廟に仕える僧侶のことを侍真と言うらしいが、侍真は12年間山籠もりをし、早暁から薄暮まで、掃除、読経、学問の仏道修行を行うという。 侍真の修行期間が長いだけ、有名な「千日回峰修行」に匹敵する大変な修行と思われるが、何故か、一般にはこの修行についてあまり知られていないようである。 |
無動寺谷 ケーブルの延暦寺駅から根本中堂の方向とは逆の南側に向かって坂を1kmほど下りると「無動寺谷」にでる。ここは、貞観7年(865年)に相応が「無動寺」を建立したことに始まるようである。無動寺谷の中心は「明王堂」であり、本尊の「不動明王像」は重要文化財に指定されている。 比叡山には千日間山を下りずに修行する有名な「天台回峰修行」があるが、ここは、その根本道場として重要な位置にある。 |
国宝殿と文化財 |
 |
延暦寺には建造物も入れて10件の国宝、64件の重要文化財が所蔵されており、建造物を除く彫刻、絵画、書跡などは、大講堂の北側に建てられている「国宝殿」で随時公開されている。 国宝で著名なものとしては、最澄の唐での通行許可書にあたる「伝教大師入唐牒」、最澄が唐の龍興寺で求得した経典や法具などの目録である「伝教大師将来目録」などが知られている。 重要文化財に指定されている多くの仏像、絵画、書跡も公開されているが、仏像では、「不動明王二童子立像」(左のコピー:国宝殿拝観券より)、「千手観音立像」などがよく知られている。 驚くことは、これら文化財の保存状態が極めて良好なことである。「伝教大師入唐牒」などは1200年の歳月を経ているものには見えない。それにしても、全山を焼き尽くしたという信長の軍勢から如何にしてこれらを全く無傷のまま護ったのであろうか。 |
比叡山に参拝したときは国宝殿を訪れ、これらの文化財を是非とも見ておきたい。 |
その他コメント 昔は霊地であったところも最近は観光地化されてしまったところが多い。比叡山もその例にもれない。これも時代の流れであろうが、比叡山頂に遊園地ができ、ドライブウエイが開通してから通俗化が加速されたようである。特に東塔地区は観光シーズンの休日ともなれば人々でごった返す。根本中堂など落ち着いて拝観するとすれば少なくとも観光シーズンの休日は避けるべきであろう。 |
| 京都の世界文化遺産一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
| 延暦寺・西塔地区のページ | 延暦寺・横川地区のページ |
Yukiyoshi Morimoto