| ホーム > 古墳一覧(古墳みてあるき) > 今城塚古墳 > 今城塚古墳第八次発掘調査 |
今城塚古墳発掘調査
(平成16年度、第八次)
| 今城塚古墳の所在地及びアクセス: 「今城塚古墳」のページを参照してください。 |
発掘調査が行われた場所など: |
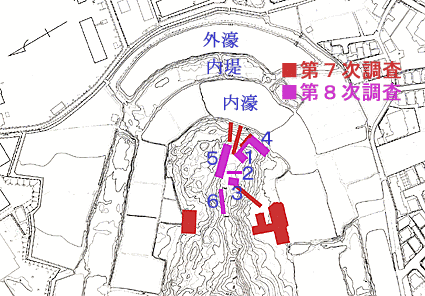 |
左のコピー(原形地図は1998年高槻市教育委員会発行「史跡・今城塚古墳」より)は今城塚古墳の発掘調査場所(第7及び第8次のみ)の図であり、ここでは今回の発掘調査に関係のある古墳後円部のみを図示した。なお、古墳全体図及び第6次以前の発掘調査場所については第7次発掘調査のページを参照して下さい。 外濠、内濠で表している部分は周濠で水の溜まっている場所である。 |
今回の第八次発掘調査が行われたのは後円部の墳頂部と後円部東南端の内濠に近接した部分で、内濠に近接した部分は第七次発掘調査の場所とかなりの部分で重複している。 直上の図で第八次発掘場所に付けられた数字はトレンチ番号である。 |
第八次発掘期間と現地説明会の様子など: |
 |
第八次発掘調査は2004年6月24日から開始され、現地説明会は2005年2月20日午前10時から行わた。 左の写真は今回の発掘調査が行われた古墳後円部の遠望である。 |
 |
左の写真は後円部の東南端で内濠に近接した場所の発掘現場(4トレンチ)での説明会の一情景である。 |
後円部東南側で内濠に近接した場所(4及び1トレンチ): |
 |
4トレンチ南側で内濠に近接した場所に径約30cmの10個の円筒埴輪列が発掘された(左の写真)。 |
 |
後円部の斜面には弧を描いた形で葺石が発掘されている(左の写真)。石材は一辺10〜40cmの川原石であり、斜面角度約40度で規則的に約1.7mの高さに積み上げられている。この川原石は近くの芥川から持ってきたものという。 |
 |
左の写真で中央下の所に開口部が見えるが、これは第七次調査(平成15年度)で発掘されたものと同じである。 左の写真中央上部に見られる墳丘内石積(後述)から墳丘斜面に沿って石組みの排水溝が傾斜角約20度の角度で下降し、排水口となっている開口部まで長さ約15mにわたって敷設されているのが発掘によりわかった。 排水溝は側石、底石、蓋石で形成されている暗渠状で、隙間には流水時に堆積された土砂が詰まっていたという。また、底石、側石には酸化鉄による褐色の着色が認められている。この排水溝は「排水溝1」と命名されている。 |
 |
左の写真は排水溝1の排水口を近接して見たものである。 第七次(平成15年度)の調査時に、排水溝の奥には石室があり、石室に溜まった水を排出するためにこの排水溝が設けられたのではないか、との推測が出されたが、今回の調査でその推測に思い違いがあったという。 これらのことから、主体部の位置や構造など現状ではわからないという。 |
 |
左の写真は1トレンチで発掘された排水溝の状況で、墳丘内石積から墳丘の裾(4トレンチ)に向かってのびている排水溝1である。排水溝が直線状であること、石組みによって暗渠状に造られているのがわかる。 |
 |
上述の排水溝1の南側約8mの場所に排水溝2(左の写真)が発掘された(4トレンチ)。 写真で排水口らしきものが見えている。葺石周辺部に排水溝の石組みが発掘されているが、墳丘部に続いていたと思われる排水溝は地震によると思われる盛り土崩壊のため、墳丘部の排水溝は発掘されなかったようである。 |
 |
墳丘内石積(1トレンチ)には一部陥没した部分が見られる。左の写真で中央部分の石積が陥没しているのがわかる。この陥没は地震によって生じたものという。 |
 |
左の写真は石棺片の出土状況(1トレンチ)である。 |
 |
左の写真は発掘調査により出土した石棺片である。 |
後円部上面中央部分(2、3及び5トレンチ): |
 |
この場所では後円部上面石群の落ち込みが発掘された。落ち込みの斜面、底には多くの石が認められている(左の写真)。この落ち込みは地震によって生じたものと考えられている。 落ち込んだ後円部上面の石は数ヶ所にまとまっているようで、石材としては花崗岩が多いという。その他、後述するように結晶片岩などが含まれており、葺石や墳丘内石積に用いられている川原石とは異なっているようである。 このことから、後円部上面の石群と墳丘内石積とは同じ目的を持って造築されたものではないと考えられている。 |
 |
5トレンチ西側には左の写真に見られるように墳頂部から地震によって滑落したと考えられる石材が認められた。 |
 |
左の写真は発掘調査で出土した石材であるが、この他、上述した石棺片も出土しているようである。 |
後円部北西部高まり部分とくびれ部(6トレンチ): |
 |
後円部で最も標高の高い場所(説明会では「高まり」という表現が使われていた)は後円部中央ではなく、後円部北西側にある。 今回の第八次調査では高まりを含めくびれ部から前方部の東端まで発掘が行われている(6トレンチ)。 左の写真で写真右端に高まりがある。高まりは盛り土によって形成されているが、そこに地滑り跡のあるのがわかる。 |
 |
左の写真は直上の写真の地滑り跡の部分を拡大したものであるが、写真右上から左下に向かって断層状の亀裂のあるのがよくわかる。 断層状部分から左側が高まりの上部からの地滑りによって出来たものであると考えられることから、かつての墳頂部は現状の高まりよりも更に標高が高かったと推察されている。 |
 |
左の写真で写真中央やや右寄りの標高の低い場所がくびれ部で、その左側が後円部、右側が前方部である。 写真で地層断面に薄い黒色の地層が見えるが、この層をはさんで盛り土の積み方が異なっているという。 |
 |
左の写真はくびれ部分の地層断面の写真である。黒色の地層が後円部(写真左側)の方へ斜め上方に向かって続いている。 黒色土層上部の盛り土部分が墳頂部まで続いていることから、高まりは古墳本来の盛り土であって後世の築城時の盛り土ではないと考えられるという。 |
古墳主体部はこれまで横穴式石室といわれているようであるが、上述したように現状では主体部の位置や構造などの状態については不明であるという。 |
2005年3月3日新規収載 |
| 古墳一覧のページ | 今城塚古墳のページ | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto