| ホーム > 西国街道沿いの史跡 > 大織冠神社 |
| ホーム > 西国街道沿いの史跡 > 大織冠神社 |
| 所在地及びアクセス: 茨木市西安威(にしあい)2丁目 |
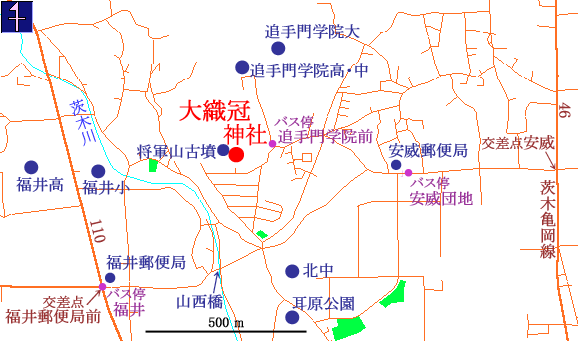 |
JR東海道線(JR京都線)「茨木」駅下車。駅北側の阪急バス「JR茨木」の1番乗り場から[86]、[87]系統「茨木サニータウン」行き、[84]系統「大岩」行き、[81]系統「忍頂寺」で乗り換え「余野」行き、のいずれかのバスに乗車し「福井」で下車する。バス停の直ぐ南側の福井郵便局前交差点を東の方向に進み茨木川に架かっている山西橋を渡り更に東の方向へ約150m進むと信号のある交差点に着く。ここから北側の住宅街に向かって坂を上がる。住宅街の中の坂を上りきったところに大織冠神社へ上る石段がある。石段を上がると正面に大織冠神社(将軍塚古墳)がある。 |
バス停「福井」を通る阪急バスの「JR茨木」発時刻は9:00〜17:00の間について次の通りである(2007年6月現在)。 |
| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
| 09 | 05# 11 31 52\ 56 | 04# 11 26 41 52\ 56 | 11 26 37\ 41 56 |
| 10 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |
| 11 | 11 26 36* 41 52\ 56 | 11 26 34* 41 52\ 56 | 11 26 34* 41 52\ 56 |
| 12 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |
| 13 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |
| 14 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |
| 15 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |
| 16 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 | 11 26 41 52\ 56 |
| 無印:「茨木サニータウン」行き、#印:「忍頂寺」行き、\印:「忍頂寺」で乗り換え「余野」行き、*印:「大岩」行き。 |
阪急京都線「茨木市」駅前からも上記同様の系統のバスが出ている。バス停「福井」を通る阪急バスの「阪急茨木」発時刻は9:00〜17:00の間について次の通りである(2007年6月現在)。 |
| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
| 09 | 01 21 43\ | 16 42\ | 02 28\ 32 |
| 10 | 02 32 43\ | 01 31 42\ | 01 31 42\ |
| 11 | 02 27* 32 43\ | 01 24* 31 42\ | 01 24* 31 42\ |
| 12 | 02 32 43\ | 01 31 42\ | 01 31 42\ |
| 13 | 02 32 43\ | 01 31 42\ | 01 31 42\ |
| 14 | 02 32 43\ | 01 31 42\ | 01 31 42\ |
| 15 | 02 32 43\ | 01 31 42\ | 01 31 42\ |
| 16 | 02 31 42\ | 01 31 42\ 57 | 01 31 42\ |
| 無印:「茨木サニータウン」行き、\印:「忍頂寺」で乗り換え「余野」行き、*印:「大岩」行き。 |
| 上記以外のアクセス法として: JR東海道線(JR京都線)「茨木」駅下車。駅北側の阪急バス「JR茨木」3番乗り場から[82]、[88]系統「追手門学院前」行のバスに乗車し終点で下車する。西の方向へ進み、住宅と山の裾の間につけられた細い坂道を登ると大織冠神社へ上がる石段下に着く(バス停から石段下まで約150m)。石段を上がると、正面に大織冠神社(将軍塚古墳)がある。 「追手門学院前」行き阪急バスの「JR茨木」発時刻は9:00〜17:00の間について次の通りである(2007年6月現在)。 |
| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜。祝日 |
| 09 | 45 | 45 | 45 |
| 10 | 45 | 45 | 45 |
| 11 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | 45 | 45 | 45 |
| 13 | 45 | 45 | 45 |
| 14 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | 20 40 | 20 40 | 20 40 |
| 16 | 15 42 | 15 45 | 15 45 |
見所など: |
 住宅地に近接して「大織冠神社」への石段の上り口がある。石段下には左の写真に見られるような『大織冠神社』と彫られた「石碑」が建てられ、また、10段ほど石段を上がったところに文政7年(1824年)銘の「鳥居」があり、一見、神社の体裁をなしているように見える。 しかしながら、後述するように石段を上りきった所には社殿があるわけではなく、実態はおよそ神社らしくない。 |
 鳥居の奥側、石段を10段ほど上がった所に、左の写真に見られるような木製の枠のようなものが石段をまたいで建てられているのが見える。 |
 上述した木製の枠のようなものを近くで見たものが左の写真である。高さは鳥居程度あるが、使われている木は太くはない。木でできた細い鳥居のようである。 このもののもつ意味はよくわからないが、ここを境にして奥側が神聖な場所、即ち霊地であり外側が俗界である、という意味の境界を表している、いわゆる結界ではないかという説がある。正しいかどうかわからないが、興味のある考えである。 |
 石段を上がりきると、正面に左の写真に見られるように「古墳」がある。「古墳」は山頂に造られた円墳で南向きの横穴式石室がある。通常の古墳とは違って、石室の開口部に格子戸が取り付けられている。 この「古墳」が造築されたのは六世紀中頃と考えられている。 |
 「古墳」の右手に『大織冠鎌足公古廟』と彫られた「石柱」(左の写真)の立っているのが見える。 藤原鎌足は中大兄皇子らと共に奈良飛鳥の板蓋宮で、専横の限りを尽くしていた蘇我入鹿を暗殺し、古代最大の政治改革、大化改新を行った人物として知られている。大織冠とは藤原鎌足が天智天皇から賜った最高の位である。 |
古くから『藤原鎌足の墓は最初摂津の阿威にあったが、後に大和多武峰に移された』との説があったようで、江戸時代になって、この「古墳」が大和に移される前の墓であるとされるようになったという。そのため、鳥居、石柱を建てて鎌足を祀った神社として、多くの人から崇められてきたようである。 この「古墳」が通常の神社でいうところの本殿に相当するものであろうと思われる。 |
 古墳石室の開口部には金属製の格子戸(左の写真)が取り付けられている。石室が神社の本殿に相当すると思われることから、内部の神聖さを保つためにこのような障壁を設けているのであろう。ただ、同じ障壁でも金属製のものは神社という概念からすれば異質のように感じられる。 |
 古墳石室の開口部に付けられている金属製の格子戸の内側に木製の格子戸(左の写真)が付けられており、石室の開口部には二枚の格子戸がある。金属製のものに比べ、木製のものは神社としての雰囲気を醸し出す効果が大きい。この格子戸には鍵がかけられるようになっているが、実際には鍵が付けられていない。 この木製の格子戸の前には、お供え物を置くことのできるスペースがある。写真でもわかるようにお供え物をのせる片木(へぎ)が置かれているが、割れており、お供え物もなく寂しいが、以前訪れたときは果物が供えられていたこともあり、時にはお参りに訪れる人もあると思われる。 |
 左の写真は石室の内部であるが、奥に小さな社が置かれている。ここに、藤原鎌足が祀られていると思われ、ご神体が安置されているのであろう。 写真でもわかるように、石室側壁の石が石室内部にせり出しており、崩れそうな感じがするが、先の阪神大震災の影響も全く見られないようで、案外丈夫な作りになっているようである。 |
上述したように、かつて、この「古墳」が鎌足の墓と考えられていたようであるが、この墓が造られたと推定される年代と鎌足の没年とが一致せず、両者の間に約100年のずれがあること、また、この墓は鎌足らが作った薄葬令に合わないこと、等から、鎌足の墓であるとすることに以前から疑問がもたれていたようである。 その後、昭和9年(1934年)に発見された「阿武山古墳」が、昭和62年(1987年)に、藤原鎌足の墓としてほぼ実証されるに至った。これらの事柄から、この「古墳」の被葬者は鎌足でないことはほぼ確実であるから、今では「大織冠」という名前がそぐわなくなっているのではなかろうか。ただ、このことについて、茨木市教育委員会名の解説掲示板には何も触れられていない。 上述したとおり、誰かがこの古墳を墓として維持している様子が伺える。鎌足の墓であることを今も信じ、祀り、維持しているのだろうか。それとも、被葬者が誰であるかを問わず、古人を敬う意味で祀っているのだろうか。 |
(参考:茨木市教育委員会名の解説掲示板) |
2007年6月15日最終更新 |
| 西国街道沿いの史跡のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |