| ホーム > 西国街道沿いの史跡 > 伊勢寺 |
| ホーム > 西国街道沿いの史跡 > 伊勢寺 |
| 所在地及びアクセス: 高槻市奥天神町1丁目 |
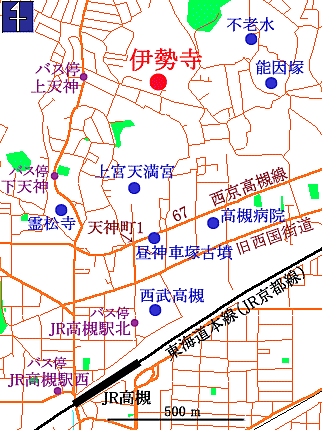 JR東海道本線(JR京都線)「高槻」駅下車。駅コンコースを北側に出て高架を下りる。高槻市営バス「JR高槻駅北」停留所4番のりばから「日吉台」、「日吉台西」行きの何れかのバスに乗車し、「上天神」で下車する。 バス停傍の信号のある交差点を東の方向に緩い坂を約300m下ると、道路左側に伊勢寺の入口が見える。 左の地図でバス停「JR高槻駅北」の場所が現状と異なっているので注意すること。 |
高槻市営バス「日吉台」及び「日吉台西」行きの「JR高槻駅北」停留所発車時刻(8:00〜17:00の間について)は下表の通りである(2004年8月1日改正、2004年11月現在)。 |
| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
| 8 | 03 12 22 32 43 55 | 10 25 40 55 | 17 37 55 |
| 9 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 54 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
見所など: |
 |
金剛山象王窟伊勢寺は曹洞宗大本山総持寺直末の禅寺である。 左の写真は「伊勢寺」境内の入口であり、車の往来する道路に面している。石段上に見えている門が山門である。 |
 |
「山門」(左の写真)は簡素な造りで、小ぶりであるが、寺の規模から見てバランスがとれている。 |
 |
「山門」をくぐると直ぐ「中門」がある(左の写真)。 通常、この「中門」は閉められているようで、「本堂」の前に出るには塀に沿って左側に進んだ所にある潜り戸を通る。 |
 |
平安時代の三十六歌仙の一人で、宇多天皇に愛され御息女にまでなった伊勢姫(877?〜939?年)が、天皇の没後、草庵を造り隠棲したのがこの地であり、伊勢姫の死後、「伊勢寺」の名で寺が創始されたといわれている。当初の宗派は天台宗だったようである。 「中門」の左手に伊勢姫の詠んだ代表的な歌の一つとされている『難波潟みじかき葦のふしまにも逢はでこの世を過ごしてよとや』(新古今和歌集)を彫った「歌碑」(左の写真)が建てられている。 伊勢寺は戦国時代に、キリシタン大名といわれた高山右近により焼き払われたと伝えられている。 |
 |
「本堂」(左の写真)には平安時代、慈覚大師の作と伝えられている本尊「聖観世音菩薩」が祀られている。 現在の堂宇は江戸時代初期、元和から寛永(1615-43年)の頃、宗永和尚により再興されたものであるといわれており、この時、伊勢寺の宗派は天台宗から曹洞宗に転じたようである。 |
 |
本堂正面には一寸変わった字体の「扁額」(左の写真)が掲げられている。 この「扁額」は江戸時代初期の心越禅師の筆跡であるといわれている。 |
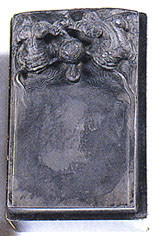 |
上述の通り、伊勢寺は伊勢姫ゆかりの寺であることから、伊勢姫が使用していたとされる丸形の五寸鏡、雌雄唐獅子珠や陶淵明の彫りのある硯(左のコピー:伊勢寺発行のパンフレットより)など、伊勢姫縁の品々が寺宝として保存されている。 それにしても伊勢姫愛用の硯など千年以上も前のものとは思えないくらい状態がよい。伊勢姫が愛用した品といわれているが、そうならば文化財の指定があってもいいのではなかろうか。 |
 |
寺の西側にある墓地の中に、伊勢姫を祀っている「伊勢廟堂」(左の写真)が建てられている。 この「伊勢廟堂」は1998年に再建されたものである。それ以前の「伊勢廟堂」は平成7年(1995年)1月の阪神大震災により、大きく損傷をうけたようである。 |
 |
廟堂の中にはかなり大きな自然石が置かれている(左の写真)。これが所謂ご神体なのであろう。 よく見るとこの石は人が座っているように見える。それも女性に見えるから不思議である。 |
 |
「伊勢廟堂」の向かって右側に高さ2m程の石碑が石で造られた亀の甲羅の上に建てられている。これは伊勢姫の「顕彰碑」(左の写真)である。 この石碑は慶安4年(1651年)に高槻藩主永井直清によって建てられ、碑文は林羅山が書いたといわれている。ただ、石碑の表面は風化をうけ、殆ど判読出来ない状態になっている。 この顕彰碑は、史跡としてどれほどの価値があるかはわからないが、風化を避けるための保存方法は考えられなかったのであろうか。尤も、自然のなすがままに任せるのも悪いことではないかもしれない。 伊勢姫が亡くなってからかなり後になるが、能因法師は伊勢姫の歌人としての才能、作風にひかれ、晩年この地に住むようになったと伝えられている。 |
 |
寺の西側墓地の中にかつての高槻城主であり、白井河原合戦で池田方に討ち取られ戦死した「和田惟政の墓」(左の写真中央)があり、史跡表示の石碑が墓石の前に建てられている。石碑では和田氏の名前が惟政ではなく維政となっている。 享保年間(1716〜36年)に高槻城を改修したときに墓石が発見され、ここに移されたという。 |
 |
和田惟政の墓碑には『前伊州太守月舩常心大・・・』の文字が見え、『元亀二年』の年号も読める(左の写真)が、かなりひどく風化しており、墓石も大きなものではなく、寂れきっている。 なお、元亀2年(1571年)は和田惟政が白井河原の合戦で討ち取られ、戦死した年である。 和田惟政の息子惟長はかつての部下であった高山右近に滅ぼされ、高槻城を乗っ取られた。 和田惟政は悲劇的な末路をたどり、しかも、死後も顧みられることが少なく不運な高槻城主である。 |
 |
寺の西側にある墓地の中には左の写真に見られるような掲示(左の写真)を沢山見ることができる。 どこの寺でも無縁の墓があると思われるが、このようにはっきりと有縁の人を探している例はあまり見ない。 |
なお、能因法師関連の史跡として、「能因塚」、「文塚」、「不老水」、「花の井」があります。詳細は、それぞれのページに記載しています。 (参考:高槻市教育委員会名の解説掲示板) |
2003年11月24日更新 |
| 西国街道沿いの史跡のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto