| ホーム > 西国街道沿いの史跡 > 普門寺 |
| ホーム > 西国街道沿いの史跡 > 普門寺 |
| 所在地及びアクセス: 高槻市富田町4丁目 |
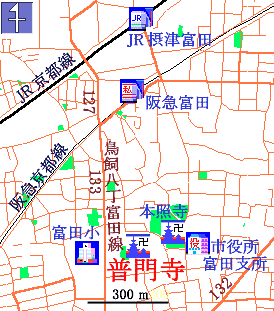 阪急京都線「富田」駅下車。南側の出口から出て線路に沿った道を西南の方向(大阪の方向)に一寸進むと、車の往来の多い道路に出るので、この道を南(左)の方向に進む。約500mで右手に富田小学校がある。小学校の傍をやり過ごし、東の方向に曲がる(左折する)と約100mで「普門寺」に着く。 JR京都線(東海道本線)「摂津富田」駅からは南出口を出て、商店街を南の方向に約200m進むと阪急京都線の踏切があるので、これを渡ると右手に阪急「富田」駅がある。 |
見所など: |
 |
左の写真は普門寺の「山門」である。大きさは寺の規模相応であり、造りは簡素である。 普門寺は明徳元年(1390年)に説厳(せつがん)によって創建されたと伝えられている。 永禄年間(16世紀後半)には室町幕府の管領(将軍の補佐役)、細川晴元や14代将軍、足利義栄もここに滞在したこともあり、別名普門寺城とも呼ばれていたようである。 |
元和3年(1617年)には龍渓和尚が普門寺に入り、約40年かけて方丈など、諸堂を建立し、当時は隆盛を誇ったといわれている。 |
 |
明暦元年(1655年)には龍渓の招きにより、明の高僧隠元禅師が約七年半の間、普門寺住持としてここに滞在したとされている。 隠元禅師は普門寺滞在中に山門から方丈の間に「石畳」を造っている(左の写真)。 隠元禅師は普門寺を出た後、京都の宇治に黄檗山万福寺を開いたことで有名である。 |
隠元禅師、龍渓和尚が去ってからは普門寺は寂れ、明治時代には堂の多くは失われ、昭和初期までは専任の住職も居なかったらしい。 |
 |
その後、復興が計られたようで、昭和57〜59年には方丈(本堂)(左の写真)の解体修理が行われ、建立当時(元和7年(1621年))の姿に復元されたといわれている。 普門寺の本尊は釈迦如来と十一面千手観音菩薩である。また、方丈の襖絵は狩野安信の作とされる水墨画であるが、残念ながら経日による画質の低下を招いている。 |
方丈(本堂)は重要文化財に指定されている。 |
 |
方丈の正面(南側)は白砂を敷いた庭園になっているが、その東隅には樹齢150年以上といわれる沙羅の木(なつつばき)が植えられており、6月中旬には白い花をつける(左の写真)。 方丈の西北側にある「池泉式枯山水の庭園」(直下の写真)は江戸時代初期、庭園造りの名人といわれた玉淵の作と伝えられ、観音補陀落山の庭といわれている。 京都桂離宮の松琴亭北園、天の橋立を造園している頃に造られたようで、その石組みがこの庭園に取り入れられているという。 |
この庭園は阿武山を借景として造られたといわれているが、今は木が生い茂っており、庭から阿武山を見通すことが出来なくなってしまっている。 |
 |
 |
左の写真は庭園の一部である。 NHKがかつてこの庭園をとりあげてTV放映したときの解説によれば、一番奥の立っている石は滝を表し、その手前の平たい細長い石は橋、橋の手前の地面で苔のない部分は川を表しているという(左の写真)。 また、この庭園に使われている石の殆どは天面が平たくなっており、尖っている石は少ない。これがこの庭の特徴の一つであるという。 |
直上の写真で左下隅に写っている石の天面は地面に対して傾斜しているが、傾斜の角度がこの庭に極めてよくマッチしているらしい。 なお、この「枯山水の庭園」は国名勝に指定されている。 |
 |
庭園の西側に普門寺城と呼ばれた時代に滞在していた細川晴元の墓と伝えられている宝篋印塔がある(左の写真)。 細川晴元は永禄6年(1563年)3月1日に死去したとされている。 普門寺は大寺院というほどの規模はないが、方丈や庭園などを拝観するとき、歴史のある名刹であることを十分に感じとることのできる寺である。 |
| 西国街道沿いの史跡のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto