| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 清水寺 |
| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 清水寺 |
| 所在地及びアクセス: 兵庫県加東市平木 |
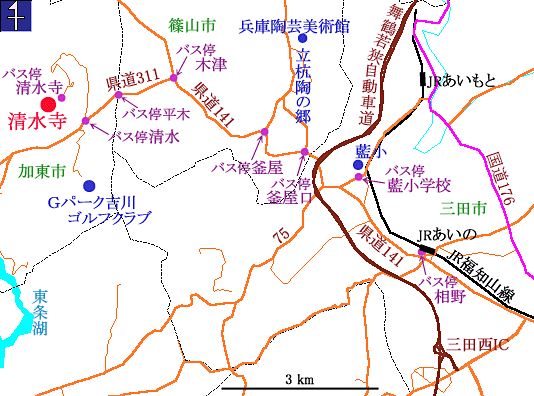 JR福知山線「相野」駅下車。駅前のバス乗り場「相野駅」から神姫バス「清水寺」行きに乗車し、終点の「清水寺」で下車する(バス乗車時間:約35分)。「清水寺」バス停は清水寺仁王門の直ぐ前にある。 バス停「清水」から終点の「清水寺」までは清水寺登山道路を通る。登山道路入口にはゲートがあり、入山料の徴収があるが、路線バスでは運転手が入山料徴収の代行をしている。登山道路はくねくねと曲がってつけられているが、完全舗装でよく整備されている。 |
清水寺行きバスの相野駅発車時刻は次の通り(2006年11月16日改正)。 平日; 10:24, 12:54 (1日2便) 土曜日・日曜日・祝日; 9:30, 10:24, 12:54 (1日3便) 相野駅行きバスの清水寺発車時刻は次の通り(2006年11月16日改正)。 平日; 12:05, 14:25 (1日2便) 土曜日・日曜日・祝日; 11:10, 12:05, 14:25 (1日3便) |
宗派:天台宗 本尊:十一面千手観世音菩薩 開基:法道仙人 縁起: |
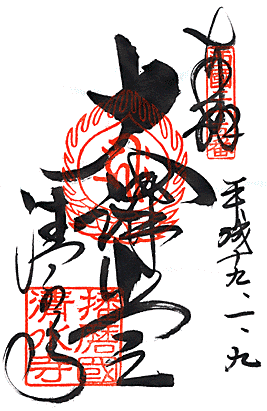 インドから渡来した伝説的な僧、法道仙人が約1800年前にこの地を訪れ、鎮護国家豊作を祈願したのが始まりで、推古天皇35年(627年)に勅願により、根本中堂を建立したと伝えられており、これが、清水寺の創始とされている。 この地はもともと水に乏しかったが、仙人は水神に祈りを捧げたところ、霊泉が湧き出したという。清水寺の名はこれに由来しているといわれている。 神亀2年(725年)に聖武天皇は行基菩薩に勅願、大講堂を建立して以来永く講経道場として重要な地位を占めたという。 明治末及び大正2年(1913年)の火災で全山焼失したことにより、現存の建物の殆どは大正から昭和にかけて再建されたもののようである。 |
境内堂宇等配置略図 直下のコピー(播州清水寺発行の参拝パンフレット記載の清水寺境内略図を基に作成)は清水寺各堂宇の配置の大略を表したものである。 |
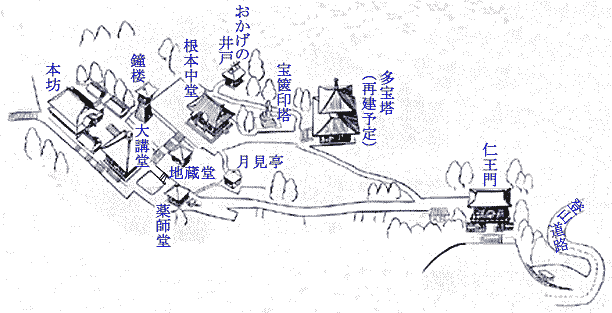 |
| 見所など: |
 バスを降りると目前に鮮やかな朱塗りの「仁王門(山門)」(左の写真)が見える。 かつての仁王門は台風で倒壊したため、昭和55年に再建、平成4年11月に塗装されたようで、新しい建物に見えるのは建てられてからそう経日していないためであろう。写真でもわかるように、門の脚部の色はピンク色であるが、平成11年(1999年)に参拝した時は、これが上部と同じ赤色だった。脚部だけ塗り替えられたのであろうか。それとも脚部だけ何らかの理由で褪色したのであろうか。 |
 「仁王門」の前、向かって右側に山号寺号が彫られた「石碑」(左の写真)が建てられている。この寺は「御嶽山 播州清水寺」とも呼ばれているが、この石碑には播州の文字が入っていない。 今では、ここまでバスや自家用車で楽に来ることができるが、かつては、麓から歩いて登っていたのであり、清水寺はかなりの難所にあったものと思われる。ただ、現在でも麓(清水バス停のところ)から歩いて清水寺まで登る参拝者がいるということである。尤も、車で来るよりも歩いて登る方が正統な参拝方法であろう。 |
 「仁王門」をくぐり、土産物屋の前を通って、スピーカーから聞こえる読経を聞きながら緩い坂を下ると、左手に「薬師堂」があり、放生池を過ぎると、「大講堂」(左の写真)の横に出る。 大講堂は縁起の項にも記載した通り、神亀2年(725年)に行基によって創建されたと伝えられている。以前の「大講堂」は大正2年の山火事により焼失したようで、現存の「大講堂」は大正6年(1917年)に再建されたものである。 |
 左の写真は「大講堂」の正面に掲げられている「寺名額」である。かなりの年月を経過した様子がうかがわれ、字は達筆であるが、この額の由来についてはよくわからない。ただ、額上部に奉納の文字が見えるので、檀家で字の上手な誰かが書いたものか、あるいは、かつての天台座主の筆によるものかもしれない。 |
 左の写真(夏撮影)は「大講堂」を根本中堂の前から見たものである。 「大講堂」は縁起の項に記載したように、聖武天皇の勅願所であり、安置されている本尊は十一面千手観世音菩薩である。 |
 「大講堂」東側(向かって右側)横の石段を根本中堂に向かって登る途中左側に「鐘楼」(左の写真)が建っている。 元の鐘楼は大正2年(1913年)の山火事で焼失し、現存の「鐘楼」は大正9年(1920年)に再建され、梵鐘はこの山上で大正8年(1919年)に鋳造されたといわれている。 この鐘の音は、播磨、丹波、摂津の国に響き渡り、開運の鐘として親しまれているという。 |
 「大講堂」東側横の石段を上まで上がると「根本中堂」(左の写真)がある。 根本中堂は推古天皇35年(627年)に勅願で法道仙人によって創建されたといわれている。 以前の根本中堂は他の堂宇と同じように大正2年(1913年)に焼失した。その後、大正6年(1917年)に再建され、入仏供養が執り行われたようである。 |
 左の写真(夏に撮影したもの)は「根本中堂」の近景である。ここの奥にある厨子の中に祀られている「根本中堂」の本尊、十一面観世音菩薩は法道仙人が刻んだ一刀三礼(いっとうさんらい:仏像を刻むのに一刀を入れる毎に三度礼拝すること)の仏像とされ、秘仏である。 この仏像は大正2年に根本中堂が全焼したときに、自ら避難し火災から免れたといわれている。これが真実ならば、約1400年も前に伝説的な僧によって造られた仏像が現存しており、しかも、自ら火災から避難したという我々の認識を超える仏像である。こんなことは事実とは思えないが・・・。 秘仏を納めた厨子の前には東京芸大名誉教授菅原安男氏の昭和58年の作とされる仏像が本尊の御前立ちとして安置されている。 |
 根本中堂の左手裏50mほど離れた場所に「おかげの井戸」(左の写真)がある。 この「おかげの井戸」は法道仙人が水神に祈りを捧げた結果、湧き出した霊泉で、清水寺の名前の由来ともなった由緒ある井戸とされている。「おかげの井戸」の周囲は木が生い茂って、薄暗い場所であり、井戸を覆っている覆い屋も古びており、何となく神秘的な雰囲気がある。 |
 「おかげの井戸」を覗き込んで自分の顔を写したら寿命が三年延びるという言い伝えがあるらしい。左の写真は井戸を覗き込んでいる人々である。覗き込んでみたが、水面が暗い上に、暗い場所に立って覗いているから、水面に顔が写ることは写るが、その表情がはっきりわかるまでには写らない。これが当たり前であると思うが、こんな写り方では寿命が延びないのではなかろうか。 |
 根本中堂の前を右方向(東の方向)に進むと「宝篋印塔」(左の写真(夏に撮影したもの))が建っているのが見える。 ここは、かつて護摩堂のあったところといわれており、この宝篋印塔には昭和9年(1934年)に神戸巡礼会の発願で般若心経の写経が3333巻納められているという。 |
 宝篋印塔の東側に小高い場所があり、ここはかつて、大塔(多宝塔)が建っていた場所、即ち大塔跡(左の写真)である。 大塔は寺の説明によれば、保元2年(1157年)に平清盛の生母と伝えられている祇園女御の建立で五智如来が祀られていたという。明治40年(1907年)に焼失、大正12年(1923年)に再建され、五間四面二層銅板葺きの建物だったようであるが、昭和40年(1965年)の台風で大破した。 多宝塔の再建計画はあるらしいが、2007年1月現在、具体的な塔の建設工事が行われているようには見えない。ただ、大塔跡にブルーシートが持ち込まれているので、何らかの工事が進められようとしているのかもしれない。 |
この地は播磨、丹波、摂津の境にあることから、しばしば争いが起こっていたらしい。山門から大講堂に向かう参道の途中右側に、切腹石が置かれているが、ここは赤松氏範らが赤松義則らに攻められ自殺した場所であるとされている。 |
御詠歌:あわれみや普(あまね)き門(かど)の品々になにをかなみのここに清水(きよみず) |
2007年2月1日最終更新 |
| 西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto