| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 勝尾寺 |
| ホーム > 西国三十三ヶ所一覧 > 勝尾寺 |
| 所在地及びアクセス: 大阪府箕面市勝尾寺2914-1 |
阪急電鉄千里線「北千里」駅下車、又は北大阪急行電鉄「千里中央」駅下車。阪急バス[29系統]「北摂霊園」行き又は「希望ヶ丘四丁目」行きに乗車する。バスは「北千里」始発で「千里中央」を経由する。「北千里」から約40分、「千里中央」から約30分の乗車で「勝尾寺」停留所に着く。「勝尾寺」バス停から寺へは直ぐ。 秋の紅葉シーズンは車も渋滞し、バスも非常に混雑するので、始発の「北千里」から乗車する方が確実。バスの運行時間も時刻通りにならないことも多い。 バスの便は少ないのでタクシーを利用する人も少なくない。 バス、タクシーを利用しない場合は阪急電鉄箕面線「箕面」駅で下車、勝尾寺まで徒歩約1時間50分。徒歩の場合は野生の猿の出没に注意すること。 |
阪急バスの「北千里」及び「千里中央」発「希望ヶ丘四丁目」行き又は「北摂霊園」行き(*印)時刻は次の通り(2010年8月現在)。特急表示のある便も勝尾寺に停車する。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪急バスの「千里中央経由北千里」行きの「勝尾寺」発車時刻は次の通り(2010年8月現在)。 |
|
バスの時刻は改訂されることがあるので、詳細は阪急バス、豊能営業所(Tel:072-739-2002)に確認されることをお勧め致します。 |
宗派:高野山真言宗 本尊:十一面千手観世音菩薩 開基:開成皇子と善仲、善算 朱印、梵字: |
 |
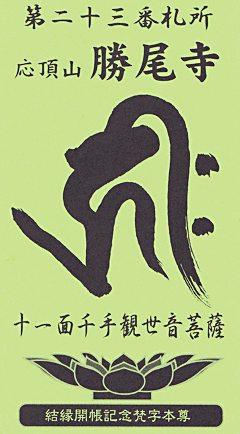 |
縁起: 双子の兄弟、藤原善仲と善算が神亀4年(727年)に庵を結び修行しているとき、一人の修行者に出会う。この修行者は光仁天皇の皇子、開成(かいじょう)皇子であった。 兄弟は般若経の書写を開成皇子に託し、相次いで世を去る。開成皇子は宝亀6年(775年)に書写を完成し、堂を建てて経を納め、十一面千手観世音菩薩を安置し、この寺を『弥勒寺』と命名したとされている。 その後、行巡上人の代に、清和天皇の病気治癒の祈祷を行い、天皇の病が癒えたことから、寺の法力が王に勝ったということで、天皇が『弥勒寺』を『勝王寺』に改名したという。しかし、寺側はあまりにも畏れ多いとして、『王』を『尾』に変え『勝尾寺』としたと伝えられている。以来、源氏、足利氏など諸将軍が勝運を祈願したところから、本寺は勝運信仰の寺として歴史的にも名をとどめることになり、現在もなお、勝運祈願のため本寺を訪れる人が多い。 |
境内諸堂配置図: |
 |
見所など: |
 勝尾寺前のバスが通る府道(4号線)に面して『應頂山勝尾寺』と彫られた巨大な山号寺号標(左の写真)が目につく。写真でもわかるように、山号寺号標に右側には札所の標識が置かれている。 |
 府道に面して左の写真のような「勅使門」が設けられているが、ここは常時閉められている。この門の20〜30m奥に勝尾寺山門がある。写真では山門の屋根だけが見えている。 境内に入るには、この門の右手にある「花の茶屋」に入り、この中を通過する。 |
 花の茶屋を通り抜けて境内に入ると、直ぐ前に楼門様式で山号である『應頂山』の額が掲げられた大きな「山門」(左の写真)が見える。 この「山門」は慶長8年(1603年)に豊臣秀頼によって再建されたもので、その後修復が行われ直近では平成8年(1996年)に修復が完了している。 |
 左の写真も「山門」であるが、「山門」を境内内側から見たものである。「山門」内側に掲げられている額には寺号が書かれているが、『勝尾寺』ではなく清和天皇が最初に命名したという『勝王寺』になっている。何故、勝王寺の寺号が書かれているのかはわからない。 |
 「山門」をくぐると池があり、参道が西北の方向に向かって延びている。 勝尾寺は箕面国定公園内にあり、秋は紅葉で有名な観光名所でもある。左の写真は1999年秋に撮影した弁天池付近の秋の紅葉風景であるが、現在は池付近の景観が撮影当時と比べ変わっている。 |
 参道を奥に進み、右手に宝物館を見るあたりから奥に多宝塔を望む石段の参道が続いている。左の写真は5月に撮影した写真で参道石段の両側にはシャクナゲの花が咲いている。 |
 石段の参道を上がると観音池のある広場に出る。観音池の中には左の写真に見られる「聖観音」像が建てられている。 この場所から高い位置に立てられている「多宝塔」が見え、ここから石段で上れば「多宝塔」に着くことが出来るが、「多宝塔」には後で訪れることにする。 広場の西にある一願不動尊の前を通り西側の広い石段参道を西の方向に向かって上がり「本堂」その他の堂宇に向かう経路を選ぶ。 |
 左の写真に見られるように秋にはこの参道の傍の楓が見事に紅葉する。写真右端に一部見えている建物は鐘楼である。 |
 石段参道を上がりきると左の写真に見られるような「勝ちダルマ奉納棚」の前に着く。この棚には大小様々な多くのダルマが納められている。 選挙に立候補し当選した人、競馬や競輪で勝った人、スポーツでライバルを制した人など、願いが叶った勝ちダルマを奉納するという。この「勝ちダルマ奉納棚」以外にも、後述するように境内にはあちこちに置かれたダルマを見ることができる。 |
 「勝ちダルマ奉納棚」に近接してその北側に「厄祓い荒神堂」(左の写真)が建てられている。 この荒神堂は日本最初の荒神社とされており、古来よりこの社の威力は各地に知れ渡っていると言われ、その霊験は数知れないほどであるという。 |
 「厄祓い荒神堂」の北側に西の方角に向かっての石段があり、これを上がると小高い場所に出て先ず「経堂」(左の写真)に出会う。写真でもわかるように見た目にかなり古ぼけた建物である。 |
 「経堂」の西側(奥側)に「薬師堂」(左の写真)が建てられている。 現存する「薬師堂」は源頼朝が建立したといわれている堂で、勝尾寺の中で最古の建物である。勿論、建立後、何回かの修理が行われているのであろう。弥勒寺といわれていた時代の「薬師堂」は金堂だったようであるが、現存する「薬師堂」と同じ場所に建っていたかどうかはわからない。 開成皇子の作と伝えられている薬師如来像と脇侍像は本尊として「薬師堂」に安置されていたが、現在、これら仏像は重要文化財に指定され「宝物館」に保存されているようである。 |
 「薬師堂」の西側に「閻魔堂」(左の写真)が建てられている。写真でもわかるように、経堂、薬師堂と同様かなり古色蒼然とした小堂である。 この場所から更に西の方向に小径が延びているが、猿の出没があるのでここから奥へ入る道は閉鎖されている。 |
以上、小高い場所に建てられている経堂、薬師堂及び閻魔堂は老朽化が見られるので、そのうちに修復が行われるものと思われる。 |
 「経堂」、「薬師堂」及び「閻魔堂」に上がる石段の直ぐ北側に「鎮守堂」(左の写真)が建てられている。 左の写真ではよくわからないが、堂の正面格子状になっている場所に勝ちダルマが殆ど隙間のない状態で置かれている。奉納棚(前述)にダルマを置く場所の余裕がないので、こういう場所にも置かれるようになったものと思われる。 |
 「鎮守堂」の北側には「開山堂」(左の写真)が建てられており、ここには、善仲、善算、開成皇子の像が安置されている。 |
 「開山堂」につけられている回廊にも左の写真に見られるように勝ちダルマが置かれている。このような状態で置かれたダルマは強風状況下で飛んで行かないのだろうか。 |
 「勝ちダルマ奉納棚」の前から北の方向に向かってつけられている参拝順路の北端に「水掛観音堂」(左の写真)が建てられている。位置的にはこの堂は「開山堂」の東側に当たる。 「水掛観音堂」の奥には水掛観音が安置されており、水子供養のためにここにお参りする人も多いようである。 |
 「水掛観音堂」に隣接して東側に建てられているのが「大師堂」(左の写真)である。 ここには弘法大師が祀られており、堂の周りには大師縁の四国八十八ヶ所のお砂踏み場が設けられている。写真左端にお砂踏み場の入口が見え、右端にはその出口が見える。 |
 左の写真は四国八十八ヶ所お砂踏み場の内部である。ずらりと並んでいる石仏は四国八十八ヶ所霊場の各本尊を模して作られたものであろう。八十八ヶ所から持ち帰った砂が足許に置かれており、これを踏むことにより各霊場にお参りしたのと同じ功徳が得られるという。 |
 「大師堂」の東側に「本堂」(左の写真)が建てられている。 「本堂」は慶長8年(1603年)に豊臣秀頼によって再建されたといわれている。その後、何回か修復されていると思われるが、見た感じから朱色も鮮やかで最近修復されたのがわかる。直近の修復は平成11年(1999年)に完了している。この修復により再建当時の姿によみがえったという。 |
 左の写真は「本堂」正面の近景である。 この「本堂」の中に当寺本尊の十一面千手観世音菩薩が祀られている。 左の写真でわかるように正面に5本の紐が下がっている。この紐はそれぞれ5色の布が束ねられたものであるが、この紐は「ご結縁紐」と呼ばれ、次のような説明が掲示されている。『この五色の紐は御本尊十一面千手観世音菩薩様の御手と直接繋がっております。そっとお触れ頂き御本尊様との御縁をお結び下さい』 「本堂」正面の格子状の障壁の桟にも勝ちダルマが置かれている。 |
 勝ちダルマは奉納棚以外の場所、堂周りなどにも多数置かれていることは既述したが、左の写真のように鐘楼の柱の根元にも整然と置かれているのを見ることが出来る。 |
 左の写真は本堂前の広場の南端にある土塀の上に置かれた勝ちダルマである。こんな場所に置かれたダルマは一寸した風でも吹き飛ばされそうな気がするのであるが・・・。それとも何か接着剤のようなもので貼り付けているのであろうか。その確認はしていない。 |
 「本堂」から見て北東側の高い場所に「二階堂」(左の写真)が建てられている。 勝尾寺は真言宗の寺でありながら、浄土宗の開祖とされる法然上人と深い関係がある。法然上人は既成の宗教集団から迫害を受け、四国に流されたが、有力な帰依者が多かったことから、約1年で配流が解かれたが、直ちに京に戻ることは許されなかったという。 |
 左の写真は「二階堂」の正面近景であるが、法然上人は承元2年(1208年)からここに逗留し、京に戻ることが許されるまで約4年間修行した場所とされている。 法然上人は京都に戻った翌年、当時としてはかなりの高齢である79才で死去したようである。 |
 「本堂」から東側に坂道を下ったところに「多宝塔」(左の写真)が建てられている。 「多宝塔」には剛界大日如来が祀られている。塔は昭和62年(1987年)に修復されており、朱色も若干くすんできているが、未だ鮮やかさを保っている。秋の季節には周囲の紅葉にとけ込んで美しい。 |
 左の写真は「多宝塔」の軒下に見られる彫刻である。花の他に馬とも羊ともつかない奇妙な動物が彫られている。 「多宝塔」横の石段を南の方向に下りると、観音池傍の広場に出る。 |
御詠歌:重くとも罪には法(のり)の勝尾寺(かちおでら)ほとけを頼む身こそやすけれ |
最終更新:2010年8月3日 |
| 西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |