| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 浄土寺 |
| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 浄土寺 |
| 所在地及びアクセス: 兵庫県小野市浄谷町 |
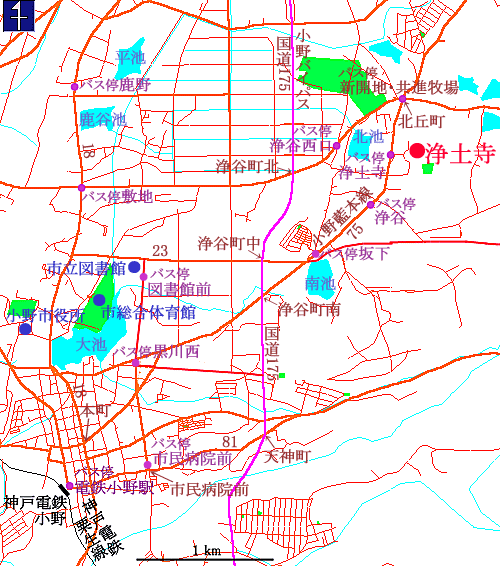 神戸電鉄粟生線「小野」駅下車。駅前の神姫バス「電鉄小野駅」停留所から、「図書館前・高山町」経由「天神」行き、又は「鹿野」行きに乗車し、「浄土寺」停留所で下車する。 バス停の東側に浄土寺の標識があり、その奥に浄土寺浄土堂の屋根が見える。 神戸電鉄は神戸の「新開地」駅から「粟生」行きが30分毎に発車しているので、それに乗車する。 「浄土寺」を通るバスの便は少ないので、場合によっては歩く方がよいかもしれない。徒歩所要時間は約1時間。 |
バス停「電鉄小野駅」から「図書館前・高山町」経由「天神」行き及び「鹿野」行きバスの発車時刻は次の通り(2005年7月現在)。バスの乗車時間は約10分間。 バスの行き先表示には「高山町経由」の表示はないが、下記の時刻表のバスは高山町経由である。下記の時刻以外に「天神」行きのバスはあるが、それらは「浄土寺」を通らないので、必ず「高山町経由」のバスに乗車すること。 |
| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
| 07 | 16 | 16 | 16 |
| 08 | 58* | -- | -- |
| 10 | 00 | 00 | 00 |
| 11 | 00 | 00 | 00 |
| 13 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | 24* | -- | -- |
| 15 | 26* | -- | -- |
| 無印:「天神」行き *:「鹿野」行き |
| 「電鉄小野駅」行きバスの「浄土寺」停留所発の時刻は次の通りである(2005年7月現在)。 |
| 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
| 07 | 26 | 26 | 26 |
| 10 | 06 | 06 | 06 |
| 11 | 51 | 51 | 51 |
| 14 | 11 | 11 | 11 |
| 15 | 36 | 36 | 36 |
| 16 | 30 | -- | -- |
| 18 | 06 | 06 | 06 |
| 注意:神姫バスのローカル路線は運行経路や時刻がしばしば変更されるようである。実際の利用に際しては、神姫バス三木営業所(電話:0794-82-3126)に問い合わせることをお勧めします。 |
宗派:高野山真言宗 本尊:薬師如来、阿弥陀三尊 開基:行基菩薩 復興:重源上人 縁起: |
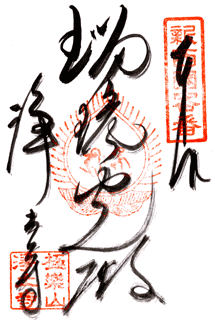 |
浄土寺の前身は現在の浄土寺の西側約2kmの場所にあった広渡寺で、奈良時代中期(西暦700年代)に行基菩薩によって創建されたと伝えられている。 その後、広渡寺は兵火にかかり荒廃していたが、後白河院の要請を受けた奈良東大寺の重源上人が建久3年(1192年)に現在の場所に復興し、浄土寺と呼ぶようになったという。 復興(中興)と同時に浄土堂、次いで薬師堂が建立され、かつては播磨高野として大いに栄えたといわれている。立地条件の悪さから、今では昔のような隆盛はないようであるが、奈良や京都にある寺院と比べて見劣りしない。 |
境内諸堂配置: |
 |
左のコピー(浄土寺のパンフレットより)は浄土寺境内の諸堂配置図(二つある塔頭を除く)である。 バス停や駐車場は図の下側(西側)にある。 |
見所など: |
 |
バス停の前が浄土寺参拝者の駐車場になっており、傍に浄土寺の大きな標識が建てられている。 この場所から奥に浄土寺のシンボルとされている「浄土堂(阿弥陀堂)」の屋根が遠望できる(左の写真)。 写真の道を直進し、突き当たりを右折すると南側から境内へ上がる石段がある。 |
 |
境内南側の石段を上がると、左手前方に「浄土堂(阿弥陀堂)」(左の写真)が見える。 「浄土堂(阿弥陀堂)」は建久3年(1192年)に建立されたといわれているが、完成したのは建久8年(1197年)という説もある。 |
何れにしても建久年間の建立であることは間違いないであろう。 |
 |
「浄土堂(阿弥陀堂)」は中国から伝来の天竺様の建築様式を持つ建物で、この様式の建物は日本では他に東大寺南大門だけといわれている。従って、天竺様の建築様式を持つ堂としては、この「浄土堂」は日本で唯一のものということになる。 天竺様の特徴は天井を貼らない化粧屋根裏や軒(左の写真)では円柱から何本も突き出ている挿肘木などに見られるという。 「浄土堂(阿弥陀堂)」は昭和32年(1957年)3月から2年半かけて解体修理が行われたようであるが、建久年間からこの時まで一度も解体修理されたことがなかったといわれている。修理前はかなり荒廃していたらしいが、約770年もの間風雪に耐え持ちこたえてきたということは信じ難い。 |
 |
堂内には「浄土堂(阿弥陀堂)」の本尊である「木造阿弥陀如来及び両脇侍立像(阿弥陀三尊立像)」(左のコピー:浄土寺のパンフレットより)が雲形の台座に立ち東向きに安置されている。 この「阿弥陀三尊立像」は浄土堂建立時に仏師快慶によって造られたものといわれており、製作当初より現在まで大きな修理はなされていないという。 阿弥陀如来はその高さ約5.3m、観音・勢至菩薩の両脇侍立像の高さは約3.7mもあり、その大きさと、造られてから800年以上も経過しているように思えない瑞々しさ、それに迫ってくるような気迫に圧倒され、感動的である。この「阿弥陀三尊立像」に感動しない人はおそらく居ないのではなかろうか。 |
 |
左の写真は西南側から見た「浄土堂」で、写真で建物の左側が堂の西面になる。 堂西面の蔀戸(しとみど)から入る夕日を背景にして堂内の阿弥陀如来を拝観するとき、さながら西方浄土から雲に乗って来迎される阿弥陀如来を眼前に見るといわれている。ただ、今回は時間の関係から西日を背景とした阿弥陀如来を拝観することはできなかった。 |
「浄土堂(阿弥陀堂)」、「阿弥陀如来及び両脇侍立像(阿弥陀三尊像)」は何れも国宝に指定されている。 |
 |
「浄土堂(阿弥陀堂)」の南側に左の写真の見られるように奇妙な動物の像(左の写真)が置かれている。 獅子のようにも見えるが、そうでもないようにも見える。一体何をイメージして作られたのかよくわからない。それに、口に何かくわえているがこれもよく分からない。かなり怖い顔をしているが、よく見るとユーモラスでもある。 |
 |
「浄土堂」の北側やや西よりの場所に「鐘楼」(左の写真)が建っている。 現存の「鐘楼」は寛永9年(1632年)に建立されたものといわれており、近年一部が修理されたようであるが、建物各部について建立当時の建築様式が見られるという。 この「鐘楼」は兵庫県文化財に指定されている。 |
 |
「鐘楼」の西側で、浄土寺伽藍の中央正面の場所に「八幡神社」(左の写真)がある。この位置から見て、重源上人が八幡信仰を重んじていたと考えられている。 写真で鳥居の奥に見えている建物は拝殿である。神社は嘉禎元年(1235年)に建てられたとされているが、現存の拝殿は当初のものではなく、遺構と考えられ、幾多の改変が加えられているようである。 |
 |
「八幡神社」の「本殿」(左の写真)は室町時代中期の代表的な建築で、桧皮葺き、三間社流造であるが、現存の本殿は当初のものではなく遺構とされている。 なお、直上の写真に見られる石柱の『郷社八幡神社』の字は満州事変当時の関東軍司令官であった陸軍大将本庄繁の書によるとされている。彼は終戦後、連合国によりA級戦犯に指定されたが逮捕される前に自殺した。 |
「八幡神社拝殿」、「八幡神社本殿」は共に重要文化財に指定されている。 |
 |
「八幡神社」の南寄り西側に「浄土堂」と相対する形で「薬師堂(本堂)」(左及び直下の写真)が建てられている。 当初の「薬師堂」は建久8年(1197年)に上棟したと伝えられている。その後焼失、現存の建物は永正14年(1517年)に再建されたものと伝えられている。 |
 |
現存の「薬師堂(本堂)」は和、唐、天竺様の折衷形式となっているようである。 「薬師堂(本堂)」の本尊、薬師如来坐像はかつて広渡寺の本尊であったが、広渡寺自体が荒廃していたため、この「薬師堂」に移し本尊として安置したとされている。 「薬師堂」が本堂と呼ばれる所以は浄土寺の前身である広渡寺から本尊が移されたことによるものと思われる。 |
「薬師堂(本堂)」は重要文化財に指定されている。 |
 |
「薬師堂」の南側に「開山堂」(左の写真)が建てられている。 「開山堂」は重源上人坐像を安置する堂である。 当初の「開山堂」の建立時期は良くわからないらしい。後に薬師堂と共に焼失たようで、その後、永正14年(1517年)に再建されたのが現存の「開山堂」といわれている。 |
 |
「重源上人坐像」(左のコピー:浄土寺のパンフレットより)は鎌倉時代に作られたとされているほぼ等身大の像で、天福2年(1234年)に奈良から移され、建長8年(1256年)にこの「開山堂」に安置されたといわれている。 像(コピー)から判断して、重源上人はかなり個性的で、意志が強く頑固、今日的な表現をすればワンマンな人であったと思われる。 本来、「重源上人坐像」はこの開山堂に安置してあるが、現在(2002年7月)、奈良国立博物館に寄託されているらしい。 「重源上人坐像」は重要文化財に、「開山堂」は兵庫県文化財に指定されている。 |
御詠歌:もうずればこの世ながらの浄土寺(じょうどてら)るり安養(あんにょう)の極楽のさと |
2005年7月20日最終更新 |
| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto