| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 酒見寺 |
| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 酒見寺 |
|
所在地及びアクセス: 兵庫県加西市北条町 |
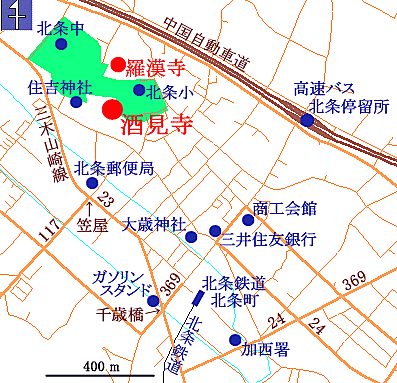 北条鉄道「北条町(ほうじょうまち)」駅下車。駅を出て西側に進むと車の通行の多い広い通りに出る。右折し北東の方向に進むと三井住友銀行傍の信号のある交差点に着くのでそれを左折する。 大歳神社を左手に見てこの道を西北の方向へ直進する。約600m進むと道路右手に酒見寺の仁王門(楼門)が見える。駅から酒見寺まで徒歩約12分。 北条鉄道はJR加古川線及び神戸電鉄の「粟生」駅から「北条町」までの鉄道で、「粟生」駅でJR加古川線及び神戸電鉄の列車とは1〜32分の待ち時間で連絡している(時刻表は下記参照)。 その他、大阪からのアクセスとしてJR「大阪」駅西口から中国自動車道ハイウエイバスで「北条」まで乗車する方法もある。 |
JR「加古川」駅及び神戸電鉄「新開地」駅から北条鉄道「北条町」駅までの連絡時間を含めての列車時刻は、「北条町」着8:00〜17:00の間について下表の通りである。【 】内は神戸電鉄の時刻、黒字は平日、赤字は土曜日・休日の時刻を表す。北条鉄道は平日、土曜日・休日共に同じ。なお、加古川線は毎月第4土曜日には線路検査などのため行き先変更や運転休止の列車があるので注意を要する。(2002年7月現在) |
|
北条鉄道「北条町」駅からJR「加古川」駅及び神戸電鉄「新開地」駅までの連絡時間を含めての列車時刻は、「北条町」発8:00〜19:00の間について下表の通りである。【 】内は神戸電鉄の時刻、黒字は平日、赤字は土曜日・休日の時刻を表す。北条鉄道は平日、土曜日・休日共に同じ。なお、加古川線は毎月第4土曜日には線路検査などのため行き先変更や運転休止の列車があるので注意を要する。(2002年7月現在) |
|
宗派:高野山真言宗 本尊:十一面観世音菩薩 開基:行基菩薩 縁起: |
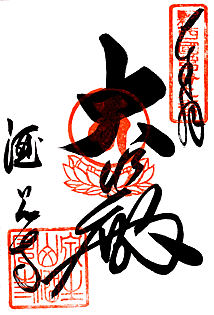 |
行基菩薩がこの地を訪れ酒見神社に詣でたところ、『寺を建てよ』とのお告げを得、このことを聖武天皇に奏上し、天正17年(745年)に聖武天皇の勅願寺として創建されたのがこの寺で、このとき、寺号を酒見寺としたと伝えられている。 なお、当時の酒見神社は現在の住吉神社である。住吉神社は酒見寺の西側に隣接している。 酒見寺は聖武天皇の勅願寺であることから、創建以来、歴代朝廷の帰依が深く、毎年勅使の参詣が行われてきたといわれている。 酒見寺は天正年間(1573〜1592年)に兵火にかかり焼失したとされており、その後、江戸時代初めに現在の形の伽藍が再建されたという。 |
見所など: |
 |
酒見寺は北側に小学校、西側に住吉神社、東側は一般住宅、南側は道路を隔てて民家、というように街の中にある。 境内南側に道路に面して「仁王門(楼門)」が建てられている。「仁王門」は楼閣形式の立派な門である(左の写真)。仁王門を通して奥に「金堂」が見える。 当初の仁王門は天正年間に焼失したあと、寛永19年(1642年)に再興されたようであるが、その後、文政8年(1825年)に再建され、これが現存の「仁王門」であるという。 この「仁王門」は江戸時代後期の建築技法がよく伝えられている建物といわれている。 |
 |
「仁王門」をくぐると参道が「金堂(本堂)」まで続いており、その参道の両側には弘法大師入定千五百年を記念して建てられたという二十一対の飾り灯篭が立ち並んでいる(左の写真)。 この飾り灯篭の列が独特な雰囲気を醸し出しており、酒見寺を印象づける役割をはたしている。 |
 |
仁王門から金堂までの参道の左側(西側)に「引聲堂」(左の写真)が建っている。 本尊は阿弥陀如来で、毎年9月10日に本尊を開帳し、一週間引聲会式が行われる。この法要は寛弘8年(1011年)に比叡山の慈覚大師により伝えられたという。 |
高野山真言宗の寺で弘法大師を祀っていながら比叡山から伝えられた法要が営まれるというのは、私のような者にはよくわからないが、心の広い寺のように思える。 |
 |
仁王門から金堂までの参道の右側(東側)に「地蔵堂」(左の写真)が建っている。 この「地蔵堂」は「水子地蔵」、「子育て地蔵」とも呼ばれているようで、本尊として地蔵菩薩が祀られている。 |
 |
仁王門から金堂までの参道の右側(東側)で地蔵堂の北側に朱塗りの「多宝塔」(左の写真)が建てられている。 縁起の項にも述べたが、当初の建物は天正年間に焼失したあと再興されたのが現在の伽藍であるとされており、現存の「多宝塔」は寛文2年(1662年)の再建になるものといわれている。 多宝塔内部を拝観することはできないが、四天柱や来迎壁には両界諸仏が描かれ、その他全面に装飾文様が極彩色で描かれているという。これらの彩色は享保13年(1728年)の頃までかけて描かれたものと考えられている。 この「多宝塔」の屋根は上重が桧皮葺き、下重が本瓦葺きで葺き方が異なっている。このような屋根は他に類型がなく非常に珍しいといわれている。 |
 |
左の写真は上重の直ぐ下側の部分であるが、この写真に見られるように、「多宝塔」の外部も台輪、組物などにも極彩色が施されている。 これらの色の鮮やかさから見て、修理・塗装が行われてから時日が大きく経過していないものと思われる。 この「多宝塔」は重要文化財に指定されている。 |
 |
上述したように「仁王門」をくぐると真っ直ぐ奥(北側)に一寸変わった形状をした二重屋根の「金堂(本堂)」(左の写真)が見える。 「金堂(本堂)」は酒見寺の総本堂にあたり、ここで諸種の法要が行われるという。 本尊の十一面観世音菩薩は行基菩薩によって刻まれたと伝えられている等身大の立像らしいが、厨子の中に安置されており通常は直接の拝観はできないようである。 |
本尊が行基菩薩によって刻まれたとすれば、由緒が正しく、しかも造られてから1200年以上も経過していることになるが、何故か文化財の指定がない。 |
 |
 |
|
直上左の写真は「金堂(本堂)」正面であり、直上右の写真は本堂前に建てられている飾り灯篭の一部である。写真では明確ではないが、賽銭箱、線香を立てる容器、また、飾り灯篭などいろいろな調度品、用具などに三つ葉葵の紋章が付けられている。 酒見寺は三代将軍家光より御朱印寺となったといわれており、これが、灯篭などに三つ葉葵の紋章が付けられている理由と思われる。 |
 |
このように徳川将軍との間の関係も深く、歴代徳川将軍の位牌が「護摩堂」に祀られているようである。 「護摩堂」(左の写真)は「酒見寺本坊」に入る門をくぐって直ぐ左側奥に建てられている。 |
 |
「金堂(本堂)」の左側(東側)に「鐘楼」(左の写真)が建っている。 現存の「鐘楼」は寛文4年(1664年)に建立されたようで、多宝塔に次いで建てられたと考えられている。 当初、外部には彩色が施され、丹塗りの痕跡があるといわれているが、現状では彩色は殆ど確認できない。 この「鐘楼」は和様を基調として、部分的に唐様を入れた建築様式で、県下でも数少ない鐘楼建築として重要な建造物であるという。 「鐘楼」は兵庫県文化財に指定されている。 |
 |
「金堂(本堂)」の裏手にあたる場所に「御影堂」(左の写真)が建てられている。「御影堂」に祀られている本尊は弘法大師である。 このように本堂の後ろに御影堂があるのは何となく不自然なような気がするが、このような配置関係は高野山にも例があるという。 弘法大師は承和2年(835年)3月21日に入定されていることに因み、毎月21日がお大師様の縁日となっている。 |
御詠歌:世の旅を酒見(さがみ)の寺にかへりみて頼むは遠き行くてなりけり |
羅漢寺(五百羅漢): |
酒見寺の西側にある住吉神社の西側の道路を北の方向に進むと、右手に小学校の敷地が見え、その北側に「羅漢寺」、通称、五百羅漢がある。五百羅漢はまた、北条石仏、加西の石仏などとも呼ばれ大分県耶馬渓山、山梨県吉沢の羅漢と共に全国的に知られている有名な石仏である。 羅漢寺はかつては酒見寺に属していたといわれている。 |
 |
羅漢寺境内入り口に仁王石像があり、拝観料をはらって奥に進むと「五百羅漢」といわれている石仏群が見える(左の写真)。 この石仏群に関しての資料、史実はなく、確かな言い伝えすらないので、いつ頃、誰が、何のために造ったのかはよくわからないという。酒見神社(現、住吉神社)の神官山氏一族の墓という説もあるらしいが証拠はないようである。 |
 |
五百羅漢といわれているが、実際の石仏数は四百余体らしい。何れにしてもその数の多さは圧巻である。 直上及び左の写真に見られるように、石仏の大きさは一定しておらず、また、左及び直下の二枚の写真に見られるように顔立ちも様々である。これら石仏の中には必ず親や子に似た顔があるといわれており、かつて、親が見たけりゃ北条の西の五百羅漢の堂にござれ、と唄われていたという。 |
 |
 |
| 石仏の彫り方はかなり稚拙であるが、それだけに野仏に見られるような素朴さがあり、これらを造った当時の人々の信仰心の深さを現在に至っても、なお窺い知ることができる。 五百羅漢は酒見寺より徒歩数分の距離にあり近接している。酒見寺を参拝したときは、ぜひ五百羅漢まで足をのばしたい |
| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto