| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 萩の寺 |
| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 萩の寺 |
| 所在地及びアクセス: |
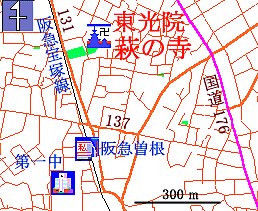
大阪府豊中市南桜塚1丁目 阪急宝塚線「曽根」駅下車。東側の出口を出て阪急電車の高架に沿って北の方向へ約150m進み、「萩の寺」の標識を見て東寄り北向きの道に入る。延命橋を渡ると直ぐ寺の山門前に着く。駅から萩の寺まで徒歩約5分。 宗派:曹洞宗 本尊:薬師如来、十一面観世音菩薩 開基:行基菩薩 |
縁起: |
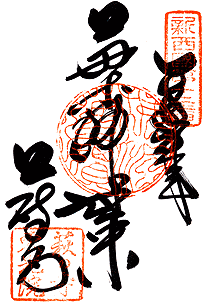 |
当寺は天平7年(735年)行基が豊崎村(現在の大阪市北区中津)に堂を建て薬師如来を祀ったことにはじまるといわれている。行基は豊崎村で民衆に火葬の方法をはじめて教えたとされており、当時、淀川水系に群生していた萩の花を供花として霊前に捧げたという。当寺が萩の寺といわれ、境内に萩が植えられている起源はここにあるとされている。 曹洞宗の籍に入ったのは延宝9年(1681年)霊全和尚が入山してからといわれている。 当寺が現在の地に移ったのは大正3年(1914年)とされており、歴史的には新しい。太平洋戦争中、食糧確保のため萩が植えられている土地をイモ畑にせよ、との圧力がかかったが、これに負けずに萩の花を守ったという。 |
見所など: |
 |
境内南側に「山門」が建っており(左の写真)、境内西側には「総門」がある。門の形、方角などから判断しておそらくこの「山門」が表門にあたるものと思われる。 「山門」をくぐると、右側は萩が植えられている「萩露園」があり、左手には「観音堂」が建っている。 |
「観音堂」内正面には厄除薬師如来が祀られ、西国及び新西国三十三ヶ所の観音像が祀られており、霊場のお砂踏みができ、堂内を一巡すれば全霊場をまわったのと同じご利益があるという。尤もこのようなお砂踏みのできる堂のあるのはこの寺に限ったことではない。 |
 |
「観音堂」の北側に「あごなし地蔵堂」が建っている(左の写真)。 ここには、「あごなし地蔵尊」が祀られているという。「あごなし」の名称は「阿古」という名の農夫の歯の病を「直し」治癒した、という縁起に基づいているらしい。この地蔵尊は秘仏であり、開扉は50年に一回とされているようである。 |
「あごなし地蔵尊」は我が国最古の地蔵尊といわれているようで、子宝を授け、寿命を伸ばすことに殊の外霊験があらたかであるという。 |
 |
境内北東の隅に「本堂」が建てられている(左及び直下の写真)。 本堂には本尊「十一面観世音菩薩像」、別名「こより十一面観音」が祀られている。 本尊の観音像は第二次大戦中また戦後の混乱期を経過したことによる傷みが激しく、昭和59〜60年(1984〜85年)に修復されたようである。 |
その時、この観音像はこよりで編んだ衣で頭から足先まで覆われ、それに漆と金箔が施された仏像であることがわかったという。 |
 |
このことから、この観音像は足利尊氏に敗れ悲劇の帝といわれている後醍醐天皇を弔って、女官たちが写経した紙でこよりを編んで着せたという「こより十一面観音」であることが判明し、戦中戦後に「こより十一面観音」が行方不明になっていたこともあり、当時大きな反響を呼んだといわれている。 昭和63年(1988年)に約1500人の人が写経した紙を切ってこよりを作り、これで衣を織り観音像に着せ昔の姿に復元したという。 本堂には他に、行基菩薩の作と伝えられているのに拘わらず、文化財の指定がない「薬師如来像」、また、重要文化財に指定されている「木造釈迦如来像」が祀られている。 |
 |
「本堂」入り口前の数段の石段を上がった所右側に「知恵の座禅石」が置かれている(左の写真)。写真では木の切り株のように見えるがこれは石である。 「知恵の座禅石」は本堂の内陣に安置されているようで、ここに置かれているのはそれの複製品と思われる。 説明によれば、「知恵の座禅石」には古代インドのサンスクリットで諸仏真言が刻銘されており、無量の福智を瞬時に成就させる霊験著しい霊石であるという。説明板には上記のような何ともすごい霊験が書かれているが、これは言い過ぎではなかろうか。 |
 |
「本堂」の前を西に進むと納経所の前に出るが、本堂と納経所との間のほぼ中間の場所、通路の北側に「正岡子規の句碑」が立っている(左の写真)。 句碑は萩の木の茂みのために見つけにくいが、石碑には萩を好んだ子規の句『ほろほろと石にこぼれぬ萩の露』が彫られている。この字は子規の筆跡を正しく模刻したものとされている。 境内には正岡子規以外にも、萩を好み萩を詠んだ多くの俳人の句碑が立てられている。 納経所の前、やや本堂に近い場所に「キリシタン燈籠」が立っているが、何故この寺にキリシタン燈籠があるのかわからない。 |
 |
境内の西北の隅に「道了堂」が建てられている(左の写真)。 「道了堂」に祀られている「道了大権現」は萩祭の祭神とされており、毎年9月15日〜9月25日に萩祭り道了祭が行われる。 道了大権現には五大誓願があり、火神、商神として霊験があらたかであるといわれており、「心願成就の道了さん」として親しまれているという。 |
 |
境内の東南部分は萩の木が植えられた庭園になっており、「萩露園」と呼ばれている(左及び直下二枚の写真)。 「萩露園」の占める面積はかなり大きく、墓地部分を除く境内全体の半分近くはあるのではないかと思われる。 |
 |
境内には、この「萩露園」以外にも、本堂横から納経堂横にかけて「白萩庭」があり(本堂の写真及び正岡子規句碑の写真参照)、寺の名称の通り境内全体に萩の木を見ることができる。 萩の名前は「生え木(はえぎ)」から来ているという。萩は生命力が強く、復活を意味する花とされており、この萩の寺以外にも境内に萩を植えている寺をしばしば見るが、このことに由来しているものと考えられる。 |
 |
なお、この「萩露園」は『大阪みどりの百選』に選ばれているようである。 萩の寺に関しての詳しい情報は「萩の寺公式サイト」を参照してください。 |
御詠歌:詣り来て袖ぬらしけり萩の寺花野にあまる露の恵みに |
| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto