| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 飛鳥寺 |
| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 飛鳥寺 |
| 所在地及びアクセス: 奈良県高市郡明日香村飛鳥682 |
近鉄南大阪線・橿原線「橿原神宮前」駅で下車する。 奈良交通バス「橿原神宮駅東口」停留所から[23]系統「飛鳥駅」行き又は[16]系統「飛鳥駅」行き([16]系統は期間限定で土曜日及び日祝日のみ運行)に乗車し、「飛鳥大仏前」停留所」停留所で下車する。飛鳥寺へは直ぐ。 バスの便は少ないので、貸自転車(レンタサイクル)を利用するのもよい。 |
「橿原神宮駅東口」発の奈良交通バス「飛鳥駅」行きの「橿原神宮駅東口」発車時刻は8時〜17時の間について下表の通り。17時以降のバスの運行はなし。この時刻は2008年4月1日改正、2008年11月現在のもの。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
宗派:真言宗豊山派 本尊:釈迦如来坐像(飛鳥大仏) 開基:蘇我馬子 縁起: |
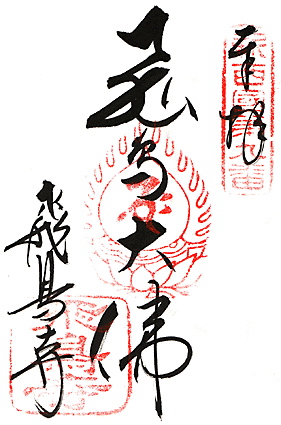 飛鳥寺は蘇我馬子が排仏派の物部守屋を倒した翌年の崇峻天皇元年(588年)に馬子が発願し、推古天皇4年(596年)に完成した日本最古の本格的寺院とされている。当初、法興寺と呼ばれ、後に元興寺に改称、更に地名に因み飛鳥寺と呼ばれるようになったといわれている。 かつては、塔を中心にして東金堂、西金堂、中金堂があり、その外側に回廊をめぐらし、更に北側には講堂を配した大寺だったという。 かっての伽藍は仁和3年(887年)及び建久7年(1196年)の火災によって塔堂すべて焼失し、室町時代以降は荒廃してしまったようである。現在は寛永9年(1632年)及び文政9年(1826年)に再建された安居院(あんごいん)と名づけられた本堂とそれに付属する建物だけの小さな寺になってしまって、かつての大寺の面影は見られない。 |
飛鳥寺創建当時の伽藍配置: |
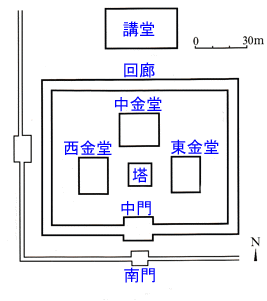 昭和31年(1956年)〜32年の発掘調査により、縁起の項にも記載したように、創建当時の飛鳥寺は南門、中門、塔、中金堂が南北直線上に並び、塔の東と西に東金堂と西金堂、それらの諸堂を取り囲む回廊と北側には講堂を配置する大寺であることがわかったという。左の図(飛鳥寺の参拝パンフレットより)は創建当時の伽藍配置を表したものである。 この伽藍配置は北朝鮮にある高句麗時代の金剛寺、定陵寺に類似しているらしい。 |
見所など: |
 飛鳥大仏バス停の西側直ぐの場所に「山門」(左の写真)が建てられている。8年前の参拝時には山門はなかったので、造られてからそう時間が経過していない。 写真でもわかるように「山門」の傍に『飛鳥大佛』の標石が立っている。標石は江戸時代寛政4年(1793年)に飛鳥寺への参拝の道標として立てられたものとされており、台石は飛鳥寺創建当時(588年)の礎石であるという。 |
 境内入口を入ると直ぐに「本堂(安居院)」(左の写真)の建物が見える。左の写真は正面(南側)から見た本堂である。 現在の「本堂」はかつての中金堂のあった位置にあたるといわれている。写真で本堂前中央付近と立て札の建ってる所に石の置かれているのが見えるが、これは創建当初(596年)の金堂の礎石とされている。 |
 左の写真は南西側から見た「本堂」である。 上述した創建当初の金堂の礎石が「本堂」のすぐ前に見える。 |
 本堂内に本尊の「銅造釈迦如来坐像」(左の写真)が祀られているが、この仏像は「飛鳥大仏」としてよく知られている 。 この「飛鳥大仏」は推古天皇14年(606年)に当時随一といわれた仏師、鞍作首止利によって造られたとされており、日本最古の金銅仏像といわれている。高さ約3m弱であるが、当時としては大仏といわれるほどの大きさだったのだろう。 本尊の現在の台座はかつての中金堂の本尊の台座跡に一致しているという。 かつての伽藍は焼失してしまったが、この本尊だけは歴史を伝えている。尤も、本尊も何回かの火災に遭っていることになるので、つぎはぎだらけになっている。写真でも修理した跡を見ることができる。原形をとどめているのは、右手中央の三指、眼元、それに左耳だけらしい。 本尊「銅造釈迦如来坐像(飛鳥大仏)」重要文化財に指定されている。 |
 本尊は拝観する位置によってその表情が変わって見えるといわれている。 左の写真は向かって右寄りの位置から見た本尊「銅造釈迦如来坐像」である。本尊は厳しい表情をしている。 |
 左の写真は向かって左寄りの位置から見た本尊「銅造釈迦如来坐像」である。本尊の表情は柔和であり優しい。 上述したように、本尊も何回かの火災に遭っており、そのために修復されつぎはぎ状態になっているが、その跡がこの写真でも明確にわかる。 |
 本堂前の広場の南寄りの場所に「塔心礎中心」(左の写真)と書かれた標識が立てられている。 推古天皇元年(593年)に舎利を心礎に納め、心柱を心礎の上に建て、推古天皇4年(596年)に塔が完成したと伝えられているが、建久7年(1196年)に落雷により、塔は他の伽藍と共に焼失したとされている。 昭和31〜32年(1956〜57年)に発掘調査が行われた結果、この場所に塔の心礎が発見された。現在、心礎はこの場所の地下3mの所に埋められているという。 発掘調査により心礎の周辺から、仏舎利の他に、管玉、金銀の小粒、銀の延べ板、勾玉、赤瑪瑙、金環、金銅の鈴、水晶の切り子玉などが発見されたといわれている。 |
 境内の西南側の隅に「鐘楼」(左の写真)が建てられている。 鐘楼は延享2年(1745年)に建立され、当初は本堂横にあったとされているが、昭和16年(1941年)に現在の場所に移されたようである。第二次大戦中の昭和18年(1943年)に鐘を供出させられ、以後、昭和33年(1958年)に新しく鋳造されるまで鐘楼には鐘がなかったという。 鐘楼は平成7年に改修工事が行われたようで、そのためか見た目には古い感じはしない。 鐘楼の鐘を撞く場所には『上は有頂天より下は奈落の底まで響けよかしと念じて静かに一度』と書かれた木札があり、鐘は自由に撞くことができる。そのためか、多客時など観光客が次々と撞き、鐘の音が絶えることはない。 |
 境内西側の出口を出て西側へ一寸進むと、旧飛鳥寺の西門跡がある。左の写真は西門跡付近から見た飛鳥寺の全景である。 |
それにしても、権勢を誇示し、気に入らないものを殺してまでも思うがままに振る舞ってきた蘇我馬子が、何故、殺生を禁じる仏教の教えの基になる寺院を建設したのであろうか。おそらく、大寺を建てることが、自分の権勢を更に誇示することに繋がると考えたのであろう。 このように考えると、この寺を創建した動機は純粋なものとは考えにくく、いろいろな人の怨念が渦巻いているであろうことは想像に難くない。 |
 西門跡の更に西側の田圃に囲まれた場所にポツンと一つ小さな五輪塔が立っている。これが「入鹿の首塚」(左の写真)である。 蘇我入鹿は皇室をしのぐほどの権勢を誇り、目に余る暴挙を繰り返したという。結局、この暴挙が命取りとなり、中大兄皇子らによって殺されたといわれている。 強力な権勢を誇示した人の塚としてはあまりにも貧弱であり、寂しい。ただ、これが入鹿の首塚というのは単なる伝説であるともいわれている。 |
御詠歌:うきことの消ゆるもけふか飛鳥寺末やすかれと祈る身なれば |
最終更新:2008年11月7日 |
| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |