| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 太融寺 |
| ホーム > 新西国三十三ヶ所一覧 > 太融寺 |
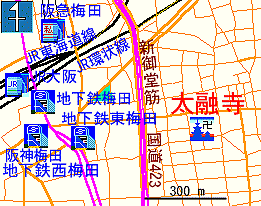 所在地及びアクセス:
所在地及びアクセス:大阪市北区太融寺町 JR「大阪」駅、阪急電鉄「梅田」駅、阪神電鉄「梅田」駅、大阪市営地下鉄御堂筋線「梅田」駅、大阪市営地下鉄谷町線「東梅田」駅、大阪市営地下鉄四つ橋線「西梅田」駅から何れも東の方向へ約400〜600m。JR「大阪」駅からは徒歩約10分。(曾根崎警察署前の広い通りを東の方向へ約400m右側(南側)) 宗派:高野山真言宗 本尊:千手千眼観世音菩薩 |
 開基:弘法大師 縁起: 弘仁12年(821年)に嵯峨天皇の勅願により、弘法大師が創建したとされている。本尊の千手千眼観世音菩薩は嵯峨天皇の念持仏だったものという。その後、淳和天皇の代、時の左大臣源融(みなもとのとおる)が七堂伽藍を建立したと伝えられており、当時は大寺院で広大な寺域を持ち、大いに栄えたようである。太融寺の寺名は七道伽藍を建立した源融に由来しているとされている。 元和元年(1615年)に大阪夏の陣で全焼、元禄年間には復興したとされているが、昭和20年(1945年)の大空襲により一宇も残さず全焼したようである。ただ、本尊の千手千眼観世音菩薩は大空襲の直前に高野山の金剛峯寺に移していたため焼失を免れたとされている。 見所など: |
 大阪(梅田)駅から太融寺に向かうと「西門」(左の写真)から寺の境内に入るのが普通であろう。この門から入ると本堂の西側面が目前に見える。 「西門」の手前右側に太融寺の七堂伽藍を建立した源融に因んで『源融公之旧跡』と刻まれた石碑が建てられている。 この「西門」は本堂の向きなどから考え太融寺の正門とは考えにくい。 |
 境内の南側には「南門」があり(左の写真)、この門をくぐると本堂の正面が目前に見える。 門の形状からみれば「西門」の方が寺の山門としてふさわしいと思われるが、本堂の正面に位置しているということからみて、この「南門」が太融寺の正門と考えられる。 写真からもわかるとおり、太融寺は大阪北の繁華街の中にあり、高層ビルの間にひっそりと佇んでいる。 |
 境内中央にある「本堂」(左の写真)は昭和35年(1960年)に再建されたものといわれている。 本堂に祀られている本尊は嵯峨天皇の念持仏だったものといわれているが、そうだとすれば、約1200年前に造られたものとなる。このように由緒のあるものが重要文化財にも指定されていないのは何故だろうか。尤もこのようなケースは他の寺院にもしばしばあるが・・・。 |
 本尊は秘仏であり、直接拝観はできないが、厨子の前には本尊と同じ姿をしているといわれている前立ちの観音像が安置されている。 境内の東北隅に朱塗りの「宝塔」が建てられている(左の写真中央の塔)。この塔の一層に「不動堂」があり、ここに「一願不動明王」が安置されている。この場所は太陽光が直接届かず、そのためにほの暗く、岩屋の上からは極く小さい滝のように水が落ちており、一種独特の神秘的な雰囲気を醸し出している。 この「一願不動明王」は諸願成就の霊験あらたかとしてよく知られているようで、お詣りする人が多い。 他に堂宇として、大師堂、護摩堂、弁天堂、鐘楼などが広いとは言えない境内に密接して建てられている。 |
 「西門」の右手、境内の北西隅に「淀殿の墓」がある(左の写真)。 淀殿は浅井長政の長女で母は織田信長の妹お市の方である。後に、豊臣秀吉の側室となり、秀頼を生む。秀吉亡き後は大阪城で豊臣方の中心人物になるが、大阪夏の陣で戦いに敗れ、秀頼と共に自刃した(元和元年(1615年))とされている。 現存の墓は六重の石塔であるが元は九重の塔だったといわれている。この石塔は太平洋戦争時の空襲に遭っているが、大きな損傷をうけなかったようである。ただ、九重の塔であったのが六重の塔になったのは空襲による破損と思われる。 当初、淀殿の墓は現在の大阪城公園内にあったようであるが、明治10年(1877年)に現在の場所に移されたという。 |
 「南門」を入った直ぐ左手に「国会期成同盟発祥之地」と刻まれた石碑が建っている(左の写真)。 明治13年(1880年)に国会期成同盟結成大会が開かれ、国会開設のための国民的運動の方向が決定、日本で最初の自由民権運動が大阪からスタートしたといわれている。 この大会の会場は北久宝寺町の喜多福亭で始まったとされているが、四日後には太融寺に移し論議されたという。 その後、この運動は全国的に展開され、国会が開設されるに至ったのであり、この太融寺は国会期成同盟発祥の地であり自由民権運動飛躍の場として記念すべく昭和60年(1985年)にこの碑が建てられたとされている。ただ、太融寺がたまたま会場となっただけと思われ、寺そのものが積極的に政治的問題に関与したと考えにくいが、このような石碑があると、太融寺が自由民権運動の主体であったように思えてくるのである。 |
御詠歌:逢ひがたき法の佳木を得たる身は苦しき海になどか沈まむ |
| 新西国三十三ヶ所一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto