| ホーム > 古墳一覧(古墳みてあるき) > 番山古墳 |
| ホーム > 古墳一覧(古墳みてあるき) > 番山古墳 |
| 所在地及びアクセス: 高槻市上土室(かみはむろ)五丁目 |
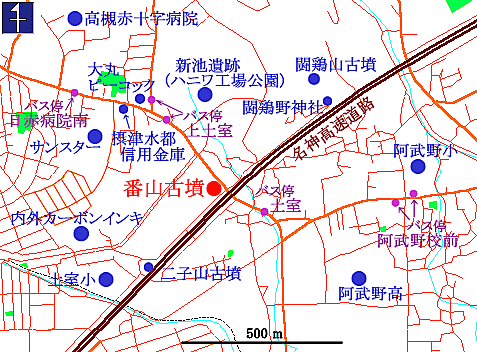 JR東海道線(京都線)「摂津富田」駅下車。駅に近接して北側にある高槻市営バス「JR富田駅」乗り場から「公団阿武山・日赤」、「日赤・公団阿武山」、「大阪薬大前」、「西塚原」行き(経由不問)のいずれかのバスに乗車し(バスの発車時刻は下記参照)、「土室(はむろ)」で下車する。バス停近くの名神高速道路の下をくぐると左手前方に番山古墳が見える。バス停から番山古墳まで徒歩2〜3分。 番山古墳から名神高速道路に沿って南西の方向に約300m進むと、二子山古墳(別ページに記載)が、また、番山古墳の北数百メートルの場所に新池遺跡(別ページに記載)、東北の方向に約500m進むと闘鶏山古墳(別ページに記載)があり、これらも同時に見学可能である。 |
高槻市営バスの「JR富田駅」発車時刻(9:00〜18:00の間について)は次の通り(2007年8月現在)。 |
| 時 | 平 日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
| 09 | 00* 05 15 25 33* 35 50 | 05 15* 20 35 50 | 05 15* 20 35 50 |
| 10 | 05 12 15* 20 35 50 | 05 15* 18 35 50 | 05 15* 20 35 50 |
| 11 | 05 15* 20 35 42 50 | 05 15* 20 35 50 | 05 15* 20 35 50 |
| 12 | 05 15* 20 35 45 50 | 05 15* 20 35 50 | 05 15* 20 35 50 |
| 13 | 05 15* 20 35 50 | 05 15* 18 35 50 | 05 15* 20 35 50 |
| 14 | 05 15* 20 35 50 | 05 15* 20 35 50 | 05 15* 20 35 50 |
| 15 | 05 15* 20 35 50 55* | 05 15* 18 30 42 54 55* | 05 15* 18 30 42 54 |
| 16 | 05 20 25* 35 45 55* | 05 15* 18 30 42 54 55* | 06 15* 18 30 42 54 55* |
| 17 | 00 10 20 25* 30 40 50 55* | 06 18 25* 28 38 48 55* 58 | 06 18 25* 30 42 54 55* |
| *印は「西塚原」行き。無印は「公団阿武山・日赤」、「日赤・公団阿武山」、「大阪薬大前」行きの何れかであるが、何れの行き先のバスでも可。「循環」表示の有無は不問。また、経由は「阿武野校前」と「宮田公民館」の二つがあるがどちらに乗車してもよい。 |
見所など: |
 上記アクセスの項に記載したように、名神高速道路の下をくぐると左手前方に古墳が見え、道路脇に左の写真に見られるように『番山古墳』と刻まれた石柱「標識」が立っている。 この「標識」の裏面に昭和18年3月に大阪府によって建てられたとの記述がある。 |
 左の写真は西側から見た「番山古墳」の全景である。平坦な場所にこんもりと茂った森のようで、一見して古墳とわかる。この地域にはかなり多くの古墳、遺跡があったとされているが、水田、道路、宅地造成などによりそれらの殆どが破壊されたようである。 |
 古墳は現状では円墳のように見えるが、濠跡等から、短い前方部をもつ帆立貝式前方後円墳(左のコピー:高槻市教育委員会名の解説掲示板の図から作成)であったと考えられている。 その直径は56m、高さは7mであり、左の図のように墳丘の南側〜東側にかけてかなり大きな溜め池が見られる。埴輪など出土品から5世紀中頃に築かれたものとされている。 |
 左の写真は直上の古墳外形図にあるAの場所から矢印の方向に向かって墳丘を見たものである。写真でもわかるように、水田が墳丘の傍まで近接している。このように、古墳の周辺が水田等になっているが、古墳自体は殆ど原形に近い形で残されている。このような古墳は数少なく、その意味で貴重な古墳であるといえる。 |
 古墳南側〜東側にかなり大きな溜め池があるが、池の外側堰堤には左に写真に見られるようなかなり丈の高い金網フェンスが取り付けられている。このフェンスは2007年になってから付けられたものである。写真で右側が墳丘である。 この溜め池は古墳の周濠の一部が残ったものと思いたいが、あるいは違うかも知れない。池には水草が生えており、渡り鳥飛来の季節には、少数ながら野鳥の姿が見られることもある。 |
 左の写真は溜め池外側堰堤にフェンスがつけられる以前の2006年に、直上の写真とほぼ同じ場所から撮影したものである。 フェンスのない方がスッキリしていて古墳の見学には望ましいが、溜め池に転落する可能性を避けるためにフェンスが取り付けられたのであろう。 |
 左の写真は古墳全体をやや西寄りの南側から見たものである。これもフェンスが取り付けられる以前の写真で、水草の生育した溜め池と古墳の位置関係がよくわかる。 |
 墳丘の南側で池の堰堤外側に数体の「小石仏」(左の写真)が置かれている。また、この場所より東側に寄った土手の斜面にも二体の小石仏が置かれている。 これらの石仏は元はどこから出土したものかはわからないが、古墳周辺に畑や水田を造る際に出土したものと考えたい。 |
 これらの「小石仏」は左の写真でもわかるように、風化の程度がひどい。写真に写っている三体のうち中央のものは顔面が何とかそれと認識できるが、左端のものなどは単に長方形の石塊のようで、石仏とは考えにくいほど風化されている。製作されてからかなりの年月が経過しているものと推測される。 |
番山古墳の被葬者については明らかではないようであるが、この地域を治めていた豪族ではないかと考えられている。 |
この古墳は高槻市の「歴史の散歩路」にとり上げられている。 (参考:高槻市教育委員会名の解説掲示板) |
2007年8月7日最終更新 |
| 古墳一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |