| ホーム > 我流観光スポット一覧 >長保寺 |
| ホーム > 我流観光スポット一覧 >長保寺 |
(紀州藩主徳川家代々の墓がある菩提寺)
|
所在地及びアクセス: 和歌山県海南市下津町上689 |
JR紀勢本線(きのくに線)「下津」駅下車。駅北側に出て北の方向に約100m進み、交差点を右折して和歌山市の方向に向かって約400m進む。斜め右に曲がりJRの踏切を渡り、国道42号線(熊野街道)に出て和歌山市方向に約400m進むと交差点「長保寺入口」に着くので、右折して道なり(県道165号線)に進む。「長保寺入口」交差点から約1.3km進むと左手に「長保寺」が見える。 「下津」駅から「長保寺入口」交差点まで徒歩約13分。「長保寺入口」交差点から「長保寺」大門まで徒歩約20分。 |
宗派:天台宗 本尊:釈迦如来坐像 開基:性空 縁起: |
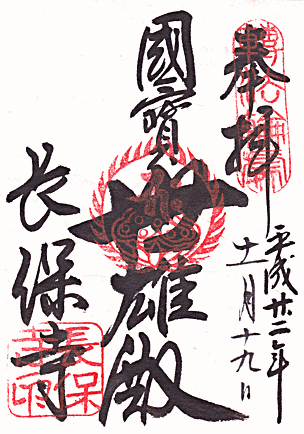 慶徳山長保寺は一条天皇の勅願により長保2年(1000年)に創建されたといわれ、開基は書写山円教寺を開いた性空と伝えられている。 創建当時は現在の場所からかなり離れたところにあったが、鎌倉時代末期に現在の場所に移り、伽藍も整備されたようである。 戦国時代になると衰退していたが、寛文6年(1666年)に初代の紀州藩主徳川頼宣が長保寺を菩提寺と決めて以来、紀州徳川家の廟所となり栄えた。 |
伽藍等境内配置図: |
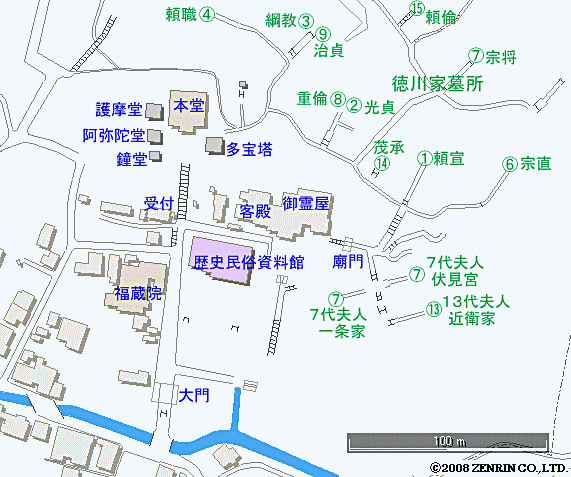 |
配置図で青字は伽藍等を、緑字は歴代紀州藩主徳川家の墓所を表す。○印内の数字は紀州藩主の代を表す。例えば、①は紀州初代藩主徳川頼宣の墓所である。 5代藩主吉宗(後の8代将軍)と13代藩主慶福(後の14代将軍家茂)の墓所は江戸にあり、長保寺にはない。なお、10代藩主治宝、11代藩主斉順、12代藩主斉彊、10代藩主夫人種姫、11代藩主夫人豊姫の墓所は長保寺にあるが、上の配置図の枠外(北側)になり記入されていない。 |
見所など: |
 県道から駐車場を横切って北に向かうと「大門」(左の写真)が見える。 この門は後小松天皇の勅願により寺僧実然が嘉慶2年(1388年)に再建したものといわれ、室町初期の特徴をよく表している代表的な門とされている。 門には仁王像が安置されているがこれは弘安9年(1286年)に堪慶によって刻まれたと伝えられている。 「大門」は昭和28年(1953年)3月に国宝に指定された。 |
 「大門」をくぐるとき入口上部に鯉の彫刻(左の写真)を見ることができる。三匹の鯉が彫られているが、この門の彫刻は左甚五郎の作と伝えられている。この説の信憑性はともかくとして、後述するように「大門」の内側の頭上同じような場所に虎と龍の彫刻があり、これと鯉の彫刻を対比して考えると面白い。 |
 「大門」を通り抜けて上部をみると虎と龍の彫刻(左の写真)のあるのがわかる。門の内側からみて左に虎、右に龍が彫られている。 龍は架空の動物であるから実際の姿は分からないが、この彫刻はイメージ的にぴったりしている。一方、虎はイメージとはかなりかけ離れた姿で彫られている。 |
 左は門に刻まれた虎の彫刻の写真である。 虎と徳川家とは関係が深いと言われ、徳川家康や初代の紀州藩主である徳川頼宣も寅年生まれという。また、一般には虎は大地の王と言われており、この門に虎が彫刻されているのは至極当然かも知れない。 |
 左は門に刻まれた龍の彫刻の写真である。 中国の故事である登竜門にちなみ、鯉が急流をのぼり龍門の滝をのぼりきって龍になり天に昇る、とうことから、登竜門をくぐれば鯉が龍になるように立身出世すると言われている。 この「大門」を登竜門に見立て、門の南側入口に鯉、これをくぐって北側に出たところに龍を彫ったのではなかろうかと思われる。 |
門の南側入口から入り、門をくぐると鯉に変身するが、参拝を済ませ帰るときにるときに北側からそのまま門をくぐると、鯉のままで立身出世をしない。帰りに門をくぐらず門の左側を通って戻ると虎になる。門の右側を通って戻ると龍になり、立身出世すると言われている。 |
 「大門」を通り抜け奥(北)に進と拝観料を納入する受付があり、傍の石段を上がると正面に「本堂」(左の写真)が見える。 「本堂」は延慶4年(1311年)の建立といわれている。本堂内には本尊釈迦如来坐像が安置されている。本尊は鎌倉時代の作といわれ、正徳4年(1714年)藩主が吉宗の時に修理されているという。 「本堂」は国宝に指定されている。 |
 「本堂」前の広場東側に「多宝塔」(左の写真)が建てられている。 「多宝塔」は鎌倉時代末期、正平11年(1357年)の建立で、ここには長保寺で最も古い仏像である大日如来が祀られている。 「多宝塔」は国宝に指定されている。 「本堂」、「多宝塔」、「大門」とつの建造物がそろって国宝に指定されているのは法隆寺と長保寺だけである。 左の写真で「多宝塔」の左側に細い道が奥に向かって延びているのが見えるが、この道を進むと紀州歴代藩主の墓所に向かうことが出来る。 |
「本堂」の北側から東側にかけて山の斜面に歴代の紀州藩主及びその夫人の墓所が江戸時代に造営された。将軍になった5代藩主吉宗と13代藩主慶福の2人を除いて28基の墓碑が1万坪の広大な土地に設けられており、すべてを回り参拝すると1時間以上の時間を要するほど規模が大きい。 徳川家墓所へお参りするには上述したように多宝塔と本堂の間にある細い道を上がってもよいが、本堂へ上がる石段下の受付のところから東側に向かう道からでも行くことが出来る。寺の案内では多宝塔の横から入って墓所を巡り、廟門を通って受付のところに戻る順路を推奨しているようである。 墓所の石垣、玉垣など石造りにはすべて花崗岩が使われ、近世大名の墓所の代表的なものであり、貴重なものとして国史跡に指定されている。 |
新規収載:2011年4月18日 |
| 我流観光スポット一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |