| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 吉田神社 |
| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 吉田神社 |
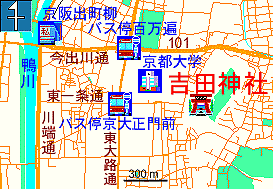 吉田神社へのアクセス
吉田神社へのアクセスJR「京都」駅から京都市バス[206]系統(東山通・北大路バスターミナル行)に乗車し、「京大正門前」で下車、東の方向へ徒歩約5分。 阪急京都線「河原町」駅、京阪「四条」駅から京都市バス[201]系統(祇園・百万遍行)に乗車し「京大正門前」で下車、東の方向へ徒歩約5分。 祭神、伝説と神徳 本社(本宮)には以下の四柱の神々がそれぞれ第一殿〜第四殿に祀られている。 |
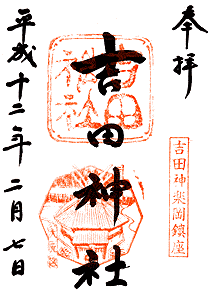 建御賀豆知命(たけみかづちのみこと) 伊波比主命(いわいぬしのみこと) 建御賀豆知命とともに天照大神(あまてらすおおみかみ)の命を受け出雲の国を支配していた大国主命(おおくにぬしのみこと)に会い、交渉し、出雲の国を譲り受けることに成功したという。これにより、建国の臣と崇められ、更に諸国を巡り国土平定の大功をたてられた神々であるとされている。 天之子八根命(あめのこやねのみこと) 天照大神が天岩戸に隠れたとき、お祈りし功をたて、また、高天原から降りた瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に従い補佐の大任にあたり大きい功績をたてた神とされ、我が国宰相の始祖とされている。また、藤原氏の氏神であるとされている。 比売神(ひめがみ) 天之子八根命の妃で婦徳の高い神とされている。 |
 由緒 貞観元年(859年)に中納言藤原山蔭が奈良の春日四神を勧請し、平安京の鎮守神として吉田山に祀ったのが神社の起源とされているようである。 かつて、皇室の崇敬厚い神社として、また、藤原氏の氏神三社の一つとして大いに栄えたという。後に、神職吉田兼倶が神道を創設し、大元宮を造営して以来益々隆盛を極め、吉田流神道の総本家として絶大な権威を持つに至ったといわれている。 |
 本宮、本殿 京大の正門前を通り、「大鳥居」(直上の写真)をくぐり、参道の突き当たりの石段を登ると、左側に神社の「本宮」(左の写真)が建っている。写真に写っているのは本宮の「四脚中門」と「御廊」である。 現存の四脚中門と御廊は寛文12年(1672年)に改造されたものといわれている。 |
 左の写真は四脚中門から見た春日造りの四棟の「本殿」である。 当初の本殿は戦火で焼失したとされており、天文3年(1534年)に新しく造営され、慶安元年(1648年)に改造されたようで、その後、現在まで数回の改修、修理が行われたといわれている。 |
 神龍社 本宮前の広場、神鹿の像の横から山上に向かって長い石段が伸びており、石段の上に吉田神社の末社「神龍社」が建てられている(左の写真)。 祭神は「大元宮」(後述)の創始者の吉田兼倶である。吉田流神道の総本家として権勢を極めたとされている人を祭神としているわりには、社は小さいが、社までの石段に因んだと思われる「百段さん」という名称で親しまれているといわれている。 吉田兼倶は永正8年(1511年)、77才で死去したとされており、「神龍社」は2年後の永正10年(1513年)に鎮祭されたという。 |
 大元宮 本宮の前を東南の方向に向かって坂を上がったところに「大元宮」が建っている(左及び直下の写真)。 大元宮は神職吉田兼倶が自邸内にあったものを文明16年(1484年)にこの地に移したものとされている。当初は斎場が設けられていたというが、吉田兼倶は神道こそ儒教、仏教の根本とし、吉田神道の根本殿堂となったとされている。 |
 以後、吉田流神道の総本家として権威をふるい、神職の任免まで行うようになったといわれている。 「大元宮」の祭神は天神地祇八百萬神(あまつかみくにつかみやおよろづのかみ)とされている。 「大元宮」の「本殿」は八角形の特異な形をしている(左の写真)。本殿の構造は道教の思想が強く現れているといわれ、八角は道教の最高神の元始天尊が支配する宇宙空間であるという。この辺の話しになると説明を聞いても素人には理解できないところがある。 現存の社殿は昭和14年(1939年)に改修され、更に、昭和55年に修理されているようである。「大元宮」は吉田神社の末社に位置付けられているが、重要文化財に指定されている。 |
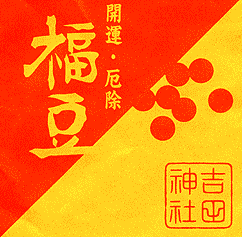 「大元宮」は節分詣発祥の社とされており、毎年2月2日〜3日には節分の神事が行われることで有名であり、厄除け祈願の参拝者が多数訪れるようである。 左のパターンは節分の時に参拝者に配られる福豆の入った紙袋であるが、この袋の裏側に『大元宮は全国の神々をまつる日本第一の霊場で、・・・』と記されている。 確かに本宮には感じられない独特の厳粛な雰囲気がこの大元宮には感じられるが、それにしても『八百萬神を祀る日本第一の霊場』という表現はすごい。 |
 竹中稲荷社 本宮の東側、吉田山(神楽岡)の頂上近くにある「竹中稲荷社」(左の写真)は、吉田神社の末社である。 この付近は本宮や大元宮から離れた場所にあるので参拝に訪れる人も少ないようである。 この付近は神楽岡といわれているように神様の居る「神座の岡」と考えられていたようであるが、江戸時代には遊楽地になったともいわれている。稲荷社の西北側に在原業平塚があるが、これは、業平が吉田山の奥に墓を造るように遺言したことによるとされている。 |
| 名神大社二十二社一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto