| �z�[�� > ���_��Г�\��Јꗗ > �匴��_�� |
| �z�[�� > ���_��Г�\��Јꗗ > �匴��_�� |
| �_�Ђւ̃A�N�Z�X�F |
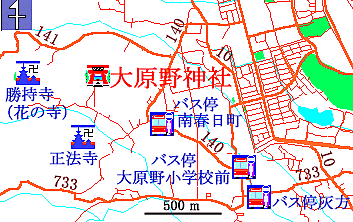 �@��}���s���u�������v�w���ԁB�w�O�̃o�X�₩���}�o�X[5�n��]�u��t�����v�s���ɏ�Ԃ��A�I�_�́u��t�����v�ʼn��Ԃ���B�o�X�₩�琼�̕��ֈꐡ�i�݁A�˂�������̎O���H�����ɂƂ�B���̒҂ɂ͍s����������W��������̂ł���ɏ]���Đi�߂Γ��H�E��ɑ匴��_�Ђ̈�̒�����������B �@�u��t�����v�o�X�₩��u�匴��_�Ёv�܂œk����15���B |
| �@�u��t�����v�s��[5�n��]��}�o�X�́u��}�������v���Ԏ�����8:00�`17:00�̊Ԃɂ��Ď��̒ʂ�i2002�N4�����݁j�B |
| �� | ���� | �y�j�� | ���j���E�j�� |
| 08 | 14�@39 | 17�@46 | 15�@46 |
| 09 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | 40 | 05�@40 | 05�@40 |
| 11 | 30 | 40 | 40 |
| 12 | 45 | 05�@40 | 05�@40 |
| 13 | 40 | 40 | 40 |
| 14 | -- | 05�@40 | 05�@40 |
| 15 | 00 | 05�@45 | 05�@45 |
| 16 | 20 | 35 | 35 |
�Ր_�A�`���F �@�ȉ���4���̍Ր_�����ꂼ����a�`��l�a���J���Ă���B ����ꓤ�q���i�����݂��Â��݂̂��Ɓj �@�����n���i�ɂɂ��݂̂��Ɓj�����V���i�����܂��͂�j����~��Ă����Ƃ��A�o�_�n���͑卑�喽�ɂ��x�z����Ă����B����ꓤ�q���͑卑�喽�ƌ����A�o�_�n��������邱�Ƃɐ����������߁A�����̐b�Ƃ��ꂽ�Ƃ����B��ɁA��錧�̎����ɒ�������ڈΐ����R�̎��_�Ƃ��Đ��߂�ꂽ�Ƃ���Ă���B �ɔg��喽�i���킢�ʂ��݂̂��Ɓj �@��t���̍�����J���Ă��镐���̐_�ł���Ƃ���Ă���B �V�V�q�������i���߂̂���˂݂̂��Ɓj �@���b���̐�c�Ƃ����A���b�����������ɂȂ�ɉh�������Ă��瓡�����̎��_�Ƃ����J����悤�ɂȂ����Ƃ����Ă���B ������_�i�Ђ߂������݁j �@�V�V�q�������̍@�Ƃ���Ă���B |
�R���F |
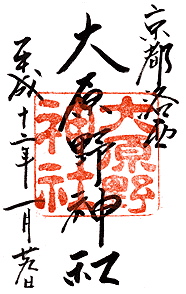 |
�@�����V�c������3�N(784�N)�ɓs��ޗǂ��璷�����ɑJ�s�����Ƃ��A�c�@�̓��������R�i�ӂ���炨�Ƃނ�j���������̎��_�ł���ޗǂ̏t����Ђ̕����匴��Ɉڂ��J�����̂��A�_�Ђ̑n�J�ł���Ƃ���Ă���B �@�匴�삪�I�ꂽ�̂́A�V�c�����肪�D���ŁA�������̒n�ɑ�������Ă������ƁA���i�����������ƁA�Ȃǂɂ��Ƃ����Ă���B �@���̌�A�Ï�3�N(850�N)�ɕ����V�c���c���A�����~�k�̊�]�����Ȃ��A�Гa�c���匴��_�ЂƖ��������Ƃ����B�匴��_�Ђ͓������̐��͂��傫�����������ɂ́A�c���M���̎Q�w������ŁA�傢�ɉh�����Ƃ����Ă���B |
�@�܂��A�������̈ꑰ�ɏ��̎q���Y�܂��ƁA���{��c�@�ɂȂ��悤�ɂ��w�肵���悤�ŁA���̎q���F��ʂ�̒n�ʂɂ��ƈ�ࣉؗ�ȍs��𐮂��ĎQ�q�����Ƃ����B �@���̌�A�헐���������A�������̐��͂̐����ɏ]���_�Ђ����������悤�ł��邪�A�c���N��(1648�`1652�N)�ɎГa���V�������c����A�����������Ƃ���Ă���B�����̎Гa�͂��̎��ɑ��c���ꂽ���̂Ƃ����Ă���B |
�_���F �@�匴��_�Ђ͋��s�䏊�̕��ʂ����������̐_�l�Ƃ��āA�܂��A�����̐_�l�A�m�b�̐_�l�Ƃ��ĐM�������Ƃ����B �@����ɁA���ɗlj��������Ă����_�l�Ƃ��Ă��M����Ă���悤�ł���B����́A�������ꑰ�ɏ��̎q���Y�܂��ƁA���{��c�@�ɂȂ��悤�ɂƂ��̐_�ЂɋF�肵�����ƂɗR�����Ă����̂ł��낤�B |
��̒����F |
 |
�@�Ԃ̉������铹�H�ɖʂ����u��̒����v�i���̎ʐ^�j�����Ă��Ă���A�k���ŎQ�q�ɂ����ꍇ�͂������狫���ɓ���B �@�����͐Α���ŁA�傫�����ʏ팩������x�ł���A�����Ƃ��땽�}�Ȋ����ł���B |
�Q�������ցF |
 |
�@�u��̒����v����u��̒����v�A�����Łu�O�̒����p�i��q�j�ւ��Q���́A�t�͍��Łi���̎ʐ^�j�A�H�͍g�t�ōʂ���B |
���̒r�F |
 |
�@�u��̒����v��������Q�������ɐi�ނƁu�O�̒����v�̎�O�E��Ɂu���̒r�v�������� �@���y�ђ����̎ʐ^�͏H�A�g�t�̋G�߂́u���̒r�v�ł���B �@���́u���̒r�v�͓ޗǂ̉���r��͂��ĕ����V�c���������Ƃ���Ă���B |
 |
�@���̒r�ɃJ�L�c�o�^�␅�@�̉Ԃ��炭����͍ł��������Ƃ����Ă��邪�A�H���g�t���������B�����A�Ԃ̍炩�Ȃ��~�̋G�߂ɂ͂������ɂ�����������������r�Ƃ͂����Ȃ��B �@�r�̖T�ɒ��X�����邪�A�~�G�͕X����Ă���悤�ł���B |
���a��F |
 |
�@�Q���ɖ��ڂ��č�����u���a���i�������j�v�ƌĂ�A����Ƃ���Ă����˂�����i���̎ʐ^�j�B �@�u���a��v�͐��a�V�c�Y���̐����Ƃ����Ă���A���āA����̉̂ɉr�܂�Ă���قǗL���ł������悤�ł���B �@�唺�Ǝ����r�w�匴�₹�����̐�����ɂނ��ђ��͖��Ƃ��V�тĂ䂩��x�Ȃǂ��悭�m���Ă���B |
�@����́u���a��v�ɂ͐��͗��܂��Ă��邪���ꂢ�Ƃ͌������A�܂��A�����N���o�Ă���悤�ɂ͌������A����Ƃ���ꂽ���̖ʉe���ÂԂ��Ƃ͂ł��Ȃ��B |
�����F �@�u���̒r�v�̉����A�Q���̉E����u�����v�Ɩ��t����ꂽ��{�̍��̖��A�����Ă���i�����̎ʐ^�j�B���̉Ԃ̍炭�G�߂ɂ͌����ȉԂ�����B�u�����v�̖��̗̂R���ɂ��Ă͂悭�킩��Ȃ��B |
 |
 |
�O�̒����A�q�a�F |
![�q�a���]](ohhara14.jpg) |
�@�u���a��v�A�u���̒r�v�A�u�����v�����Ȃ��牜�i�ނƑN�₩�Ȏ�F�ɓh��ꂽ�u�O�̒����v������A���Ɂu�q�a�v��������i���̎ʐ^�j�B |
 |
�@�u�q�a�v�͍��̎ʐ^�Ō�����悤�ɓ��ɕς�������̂ł͂Ȃ��A���̋K�͂��傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�i���̂���_�ЂƂ������Ƃł����Ƒ傫�����X�Ƃ����q�a��z�����Ă����̂ł��邪�E�E�E�B |
���̍��� �@�q�a�̑O�ɂ��鍝���́A�{��̕\��������������q�����ʂł��邪�A�匴��_�Ђ̔q�a�̑O�ɂ��鍝���͂��܂������Ȃ��u���̍����v�ł���A�������č����������A�E���̂��Y���ł���i�����̎ʐ^�j�B |
 |
 |
| �@�S���{��̕\��̂Ȃ����̍����́A���̐_�Ђ̎��S�̓I�ȕ��͋C�������I�ȃ��[�h�Ɏd�グ�Ă���B������A���̐_�Ђ̑n�J���c�@�̈ӎu�Ɋ�Â������ƂɗR�����Ă��邽�߂��낤���B |
�{�a |
 |
�@���̎ʐ^�͔q�a���猩���{�a�̈ꕔ�ł���A���ɓ�̎Ђ������Ă���B |
 |
�@����̎ʐ^�Ɍ������̎Ђ̌������ĉE���ɍ��̎ʐ^�Ɍ�����悤���q��������A�X�ɂ��̉E���ɓ�̎Ђ�����B �@�ȏ�A���v�l�̎Ђ��{�a�ɂȂ��Ă���A�Ր_�̍��ɋL�ڂ����l���̍Ր_�����ꂼ��̎Ђ��J���Ă���悤�ł���B |
| ���_��Г�\��Јꗗ�̃y�[�W�֖߂� | ���̃y�[�W�̐擪�֖߂� |
Yukiyoshi Morimoto