| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 内宮 |
| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 内宮 |
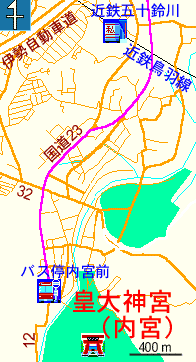 内宮へのアクセス
内宮へのアクセス内宮への最寄りの鉄道の駅は近鉄鳥羽線の「五十鈴川」駅であるが、伊勢神宮への参拝は先ず「外宮」に詣り、次いで「内宮」に詣るのが普通のコースとされているので、それに従うことにする。 外宮神域入口から道を隔てて三重交通バス停「外宮前」があり、ここから「内宮前」行きのバスに乗車し、終点の「内宮前」で下車する(乗車時間約15分、運賃は410円(2000年7月現在)で高額感あり)。バス停から内宮神域入口の宇治橋まですぐ。 バスの運行頻度は8〜18時の間、1時間に4便(15分毎)(2000年7月現在)。 なお、このバスは伊勢市駅、近鉄宇治山田駅、近鉄五十鈴川駅を経由して内宮前、外宮前を循環運転しているので、これらの駅前からも乗車可能である。 祭神 天照大御神(あまてらすおおみかみ) 皇室の祖神であり、一般国民の総氏神とされている。神様の中でも別格であり、あまりにも畏れ多いためか具体的な神徳は示されていないようである。 |
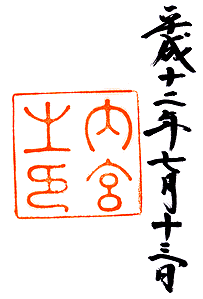 由緒、伝説 当初、天照大御神は皇室に祀られていたが、今から約2000年前に垂仁天皇の皇女、倭姫命(やまとひめのみこと)が大御神の鎮座にふさわしい土地を探した結果、伊勢のこの地が大御神の意に叶う土地として選ばれたと伝えられている。 祭神が皇室の祖神ということでもあり、かつては皇室以外の参拝は許されていなかったようであるが、神官の努力により室町時代には将軍や武将も参拝できるようになり、やがて、一般民衆も参拝可能になってきた。戦国時代には一時衰えたようであるが、江戸時代になると伊勢詣りはブームになったといわれ、真偽のほどは不明であるが、幕末には年に一千万人ちかくの人が参拝に訪れたという。 なお、伊勢神宮は最高の格式を持つ神宮とされ、正式には「神宮」といい、伊勢という言葉をつけないとされている。 |
 大鳥居、宇治橋 五十鈴川にかかっている「宇治橋」を渡って内宮神域に入る。橋の西端と東端にそれぞれ「鳥居」が立っている(左の写真)が、これらの鳥居は遷宮(後述)の際、解体された外宮と内宮の正殿の柱が利用されているといわれている。 内宮の鳥居は、外宮の鳥居と同様、一般の神社で見られるような朱に塗られていない。 「宇治橋」は檜造りであり、通行は左右に分離されており、中央の分離帯はやや高く造られている。この中央の部分は神様が通る道であるという。 |
 御手洗場 参道を進み、火除橋次いで一の鳥居をくぐると「御手洗場(みたらし)」がある。 左は「御手洗場」から「五十鈴川」を見た写真であり、この場所で手を清めるのがオーソドックスな参拝方法といわれている。ただ、日によっては川上で工事が行われていることがあり、川が濁って手洗いに適さないこともある。 この場所には石畳が敷きつめられているが、これは徳川綱吉の母、桂昌院の寄進によるとされている。 |
 神楽殿 「御手洗場」を通り、100m余り進むと左の写真に見られる銅板葺きの大きな建物、「神楽殿」に着く。 ここには神楽の演奏などを行う本来の「神楽殿」の他に、お札類の授与が行われる「神札授与所」も併設されている。 |
 正宮までの参道 御札授与所、神楽殿の前を通り、参道を進むと左の写真に見られるように、参道の中に大きな杉の木が生えているのを目にする。参道の周辺は杉を主体とした木々が生い茂り鬱蒼とした森を形成している。 ただ、ガイドブックには『・・・静かな杉木立の間に玉砂利を踏む音だけが聞こえる。・・・』と書かれているが、多数の観光客など参道を行き来する現状からは、とてもガイドブックに書かれているような静寂感が望めるような状況ではない。 正宮 参道の突き当たり左手に石段があり、石段の上に「正宮(しょうぐう)」がある(直下の写真)。 |
 内宮の正宮も外宮の正宮と同様、「正宮」内には「東宝殿」、「西宝殿」、「正殿」などの社殿が建てられているようであるが、外からは正宮の内部を見ることはできない。参拝は外玉垣南御門の絹の帳の下がった前の拝所で行う(写真)。 これは一般的に言えることかもしれないが、「正宮」(一般的には本殿)を人々の目から隠すのは何故なのだろうか。正宮内が見えることが神宮自体の厳粛さを失うことになるのだろうか。 また、これも奇妙なことで理由はよくわからないが、写真撮影は石段の下で行うことと定められている。石段の下と石段を上がった所とでは写真撮影上どんな違いがあるのだろうか。 直下の写真は正宮内社殿の屋根の一部分で、「御稲御倉」(後述)の前から見たものである。 |
 「正宮」の隣に密接して西側に、正宮と同じ位の面積を持つ空き地がある。ここは遷宮により、次の「正宮」が建てられる場所とされている。外宮の場合も同じであるが、「正宮」は20年ごとに建て替えが行われるようで、「遷宮」と呼ばれている。 最初の内宮の遷宮は持統天皇4年(690年)に行われ、以来、1300余年続いているといわれている。最近の第61回遷宮は外宮、内宮共に平成5年(1993年)に行われた。 |
 御稲御倉 「神楽殿」の前を「正宮」の方に少し進むと左側に入る小路がある。この路は「荒祭宮」(後述)に通じているが、その途中に「御稲御倉(みしねのみくら)」が建てられている(左の写真)。 これは稲を納める倉といわれている。この社殿は参拝者にあまり注目されていないようであるが、建築様式が正殿と同じ「唯一神明造」の特徴を持っており、興味深い社殿である。 高床式建築で棟の両端を支える棟持柱があり、屋根は茅葺きで、千木がつけられ、棟の上には鰹木(かつおぎ:屋根の上にある丸太状の木)が並んでいる。 「御稲御倉」につけられた鰹木は6本であるが、「正殿」の鰹木は10本あるらしい。内宮の社殿につけられている鰹木の数は偶数であるが、外宮の社殿につけられているそれは奇数といわれている。 |
 荒祭宮 「御稲御倉」の前を通り、「正宮」の裏手を通り石段を下りると、内宮の第一別宮である「荒祭宮(あらまつりのみや)」の前に出る(左の写真)。 祭神は「天照坐皇大御神荒御魂(あまてらしますすめおほみかみのあらみたま)」即ち正殿の祭神、天照大御神の荒御魂(荒く猛き神霊)である。 「荒祭宮」の前の石段には「踏まぬ石」がある。石の割れ目が天の字に見えることから、天から降ってきた石といわれ、踏んではならないという。 内宮周辺 内宮前バス停から宇治橋を渡らず、五十鈴川に沿って北の方向に進むと、「おはらい町」があり、その一角に「おかげ横丁」がある(直下の写真)。 |
 この場所に電柱は一本もなく、江戸時代の門前町の雰囲気を出すことに苦労しているが、内容は土産物屋の通りに過ぎず、売っているものが現在風で、歩いている人々がこれまた流行のものを身につけているのであるから、無理をして(?)このような街並みを造った意味がどれだけあるのだろうか、と考えたくなる。 |
| 名神大社二十二社一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto