| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 春日大社 |
| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 春日大社 |
| 春日大社へのアクセス |
近鉄奈良駅下車。広い道(国道369号線)を東の方向に進み、国道169号線の下をくぐり、右手に奈良国立博物館を見ながら更に東に進むと、大仏前交差点で春日大社参道の標識が見える。参道を道なりに進むと「春日大社」に着く。駅から春日大社まで徒歩約25分。 国道169号線の下をくぐらず、県庁東交差点を右折し(南側に曲がる)、約250m南下すると左手に「一の鳥居」が見える。これをくぐり東の方向へ直進すると「春日大社」に着く。この道程は上記よりも若干時間がかかるが、表参道を通ることになるのでこちらのほうが道筋としては正しいかもしれない。 |
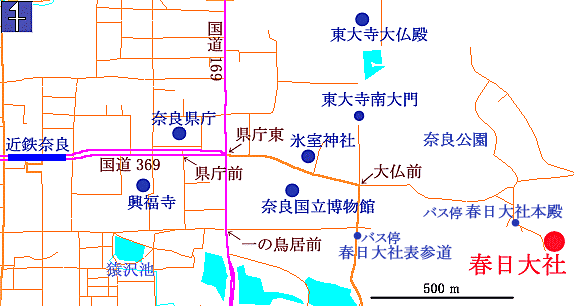 |
| 近鉄奈良駅又はJR奈良駅から、春日大社本殿行き又は春日大社表参道を通る市内循環バスが運行されているので、これらを利用することも可能であるが、少なくとも参道は歩いて通り、奈良公園内参道の雰囲気を味わうべきであろう。 |
祭神 武甕槌命(たけみかづちのみこと) 向かって一番右側の本殿(第一殿)に祀られている。 経津主命(ふつぬしのみこと) 右から二番目の本殿(第二殿)に祀られている。 経津主命と武甕槌命は、天照大神の子孫が高天原から降臨するに際し、大國主命ほか多くの神様と和平を結ぶ功績のあった神様とされている。 天児屋根命(あめのこやねのみこと) 右から三番目の本殿(第三殿)に祀られている。 天児屋根命は天の岩戸に籠もった天照大神を岩戸からお出ましを願うために、お祭りを行った神様といわれている。 比売神(ひめがみ) 一番左側の本殿(第四殿)に祀られている。 由緒、神徳 |
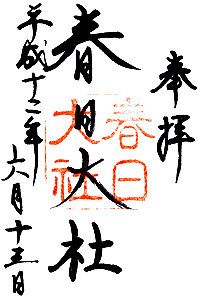 |
鹿島神宮(現茨城県)に祀られていた武甕槌命を春日山(御蓋山)の頂上に移し国土安穏、国民繁栄を祈り祀ったのが春日大社の創始とされているようである。 神護景雲2年(768年)には御託宣により、武甕槌命の他に、香取神社(現千葉県)に祀られていた経津主命、枚岡神社(現大阪府)に祀られていた天児屋根命と比売神の三柱の神様を加え、四柱の神様として現在の地に社殿を造営し祀ったといわれている。 春日大社はもともと藤原北家の氏社として創建されたようで、平安時代には藤原北家の隆盛と共に拡充され、大いに栄えたという。 一条天皇が永祚元年(989年)に行幸して以来、天皇の行幸がたびたび行われたらしいが、平安中期以降から明治の神仏分離までは興福寺が運営の実権を握っていたといわれている。 |
春日大社の祭神は慈悲萬行の神として崇敬されており、例祭には五穀豊穣の祈願が行われている。 |
一の鳥居から南門まで |
 |
三条通と国道169号線が交差する一の鳥居前交差点のところに「一の鳥居」(左の写真)が建てられている。 鳥居自体も大きいが全体のスケールに比べ柱の太いのが特徴的である。ここから東側(奥側)が春日大社の参道になっている。 「一の鳥居」は重要文化財に指定されている。 |
 |
「一の鳥居」からかなり離れて建てられている「二の鳥居」をくぐると「手水場」(左の写真)がある。 普通、手水場の水は竹筒から出ているのをよく見かけるが、ここの手水場の水は写真でもわかるように鹿の像が口にくわえている筒から出ている。春日大社であるから鹿は当然かもしれないが・・・。 |
南門から神拝所(幣殿・舞殿) |
 |
参道を東に進み、二の鳥居をくぐって暫く歩き、短い石段を上がると鮮やかな朱塗りの大きな「南門」(左の写真)に着く。 当初はこの場所には鳥居が立っていたとされているが治承3年(1179年)に楼門に改められたという。 「南門」に接している「回廊」は写真撮影の時点で改修工事中であり、見栄えに若干難点があった。 「南門」は重要文化財に指定されている。 |
 |
南門の前に「神石」と呼ばれ、柵で囲われている石がある(左の写真)。地表に出ている部分は小さいが地下の部分の大きさはわからない。 この石は太古の昔、神様が降臨する憑代(よりしろ)として祀られた磐座、又は、春日若宮の祭神がここから現れたとされる出現石、或いは、宝亀3年(772年)の落雷により落下した社額を埋めた額塚など、諸々の伝説があるが、神がかりの石として触れることができないように囲われている。 |
 |
「南門」をくぐると正面に「神拝所」(左の写真)がある。「神拝所」は「幣殿」と「舞殿」が一棟になった建物である。 「神拝所」は奥にある本殿を参拝する場所であり、ここから参拝する場合は特に参拝料は不要である。 この「幣殿・舞殿」は重要文化財に指定されている。 |
中門、御廊、本殿 |
 |
「神拝所」(「幣殿・舞殿」)の奥に朱塗りで荘重な造りの「中門」(左の写真)と中門を挟んで左右に「御廊」が伸びているのが見える。 「神拝所」から参拝する際は参拝料は不要であるが、「中門」の前まで行って本殿を参拝するためには社頭特別参拝料金を支払わなければならない。 「中門」の奥に四棟の「本殿」が建てられているが、「中門、御廊」の外からは僅かに千木が見える(写真で御廊の奥、右端に見える)程度であり、本殿全体を見ることはできない。 「中門」内中央に春日大社で最大の釣金燈籠が下がっている。これは近衛篤麿の奉納によるものという。 |
「中門、御廊」の前にある木製の柵は「稲垣」と呼ばれ、稲穂をここに掛けて神前にお供えするとされている。また、その手前の四基の燈籠は「春日燈籠」と呼ばれている形式のものといわれている。 |
 |
左の写真は「御廊」を西端から見たもので、写真中央付近に中門の屋根、石段の右側に「稲垣」が見える。 |
 |
「本殿」は向かって右から第一殿から第四殿まで四つの社が並んでいるが、上述のように「本殿」を正面から直接見ることが出来ない。 裏手にまわると左の写真にあるように、「本殿」の屋根の一部が見えるが、全体像は見えない。 「中門・御廊」は重要文化財に、四棟の「本殿」は国宝に指定されている。 |
移殿(内侍殿)、直会殿 |
 |
御廊前の西側の石段を下りた先に「移殿(内侍殿)」が建っている。左の写真は移殿の内部で2000年6月に撮影したものであるが、2002年9月には内部は撮影禁止になっていた。 ここは20年に一度の本殿の造り替えの際、四柱の祭神を移すための建物といわれている。 |
 |
「移殿(内侍殿)」の南側に「直会殿」が建っている。左の写真は建物西側から見た「直会殿」である。 写真でもわかるように、軒下には多数の灯篭が吊り下げられており、他の社殿と異なる一寸変わった雰囲気を持っている。 春日祭に勅使一行がここで直会の儀を行うとされている。 「直会殿」は重要文化財に指定されている。 |
回廊 |
 |
春日大社には主な社殿を取り囲むように回廊がつけられている。左の写真は「西回廊」であり、朱塗りの回廊には多数の燈籠が吊り下げられており、回廊中央部は通行できない状態である。回廊の造りは東西南北の四つの回廊とも基本的に同じである。 南回廊には上述の「南門」、西回廊には「内侍門」、「清浄門」、「慶賀門」の三つの門が付けられており、回廊には合計四つの門が設けられている。 |
「南門」は重要文化財に指定されていることは上述したが、「回廊」、「内侍門」、「清浄門」、「慶賀門」共にいずれも重要文化財に指定されている。 |
御間道(おあいみち)と石燈籠 春日大社には61社の摂社、末社があるといわれているが、それらの中で最も規模が大きく著名なのは「若宮神社」であろう。 |
 |
若宮神社へは春日大社南門前から東南の方向へ「御間道(おあいみち)」を通って行く。「御間道」には左の写真に見られるように、「御間型燈籠(おあいがたとうろう)」がビッシリと並んで立てられており、これが独特の雰囲気を醸し出している。 |
宝物殿と文化財 |
 |
「二の鳥居」の北側にある「宝物殿」には春日大社所蔵の国宝、重要文化財をはじめ寺宝が保存されており、期間を決めて一般公開している。 宝物殿の入口を入ったところに、「御間型燈籠」が置かれている(左の写真)。この「御間型燈籠」は元享3年(1323年)に造られたもので最も古いものといわれており、造りも優れていることから重要文化財に指定されている。 春日大社所蔵の国宝、重要文化財の数は非常に多い。たとえば国宝に指定されている「本宮御料古神宝類」は一括して表されているが、その内容は37種類に及んでいるようである。弓、矢、太刀などの武器、化粧道具、楽器類などが含まれている。その他、国宝に指定されている文化財として「若宮御料古神宝類」、「金地螺鈿毛抜形太刀」ほか数振りの太刀、「赤糸威鎧」などがある。 公開期間には全ての文化財が展示されているわけではないが、多数の国宝を含む神宝が展示されているので、その際はぜひ拝観見学すべきであろう。 |
神苑 |
 |
本社までの参道の途中にある「神苑」は参拝者にやすらぎを与える神様の庭として、現在は一般に公開しているが、もとは、万葉植物園として昭和7年(1932年)に開園されたものといわれている。 苑内にある池の中の中之島には「遥拝石」(左の写真)が置かれ、その前には朱塗りの「浮舞台」が設けられている。ただ、この舞台は池の上にあるが水の上に浮いているわけではない。「遥拝石」はかなり大きな石で表面に「神」と彫られているが、これがあまりにも直截的で単純、見方によっては幼稚である。こういうものには何も書かない方がよいのではないか。 苑内には多くの木や草花が植えられており、季節毎にそれぞれの草木が花をつけるようであるが、入苑料を支払ってでも、神苑を見学する価値があるか否かは主観のわかれるところであろう。 |
| 名神大社二十二社一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto