| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 日吉大社 |
| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 日吉大社 |
| 日吉大社へのアクセス |
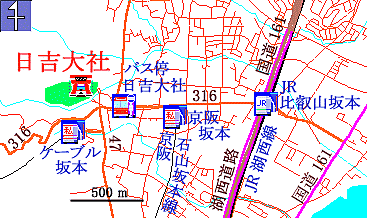 JR湖西線「比叡山坂本」駅下車、湖西道路の高架下をくぐり西の方向に進む。石造りの鳥居を二つくぐり、先に進むと日吉大社の赤い鳥居に着く。駅から徒歩20〜25分。 京阪電車石山坂本線「坂本」駅下車、広い通りに出て西の方向に進むと、徒歩約10分で日吉大社の赤い鳥居に着く。 JR「比叡山坂本」駅から「石山駅」行き、「西教寺」行き又は「ケーブル坂本駅」行きに乗車し、バス停「日吉大社前」で下車すると、境内入口まで直ぐであるが、バスの便が少ない(下記)ので歩く方がよい。 JR「比叡山坂本」駅から「日吉大社前」を通るバスの時刻(「JR比叡山坂本駅」発8時〜17時の間について)は次の通り。なお、「ケーブル坂本駅」行きは期間運転のため運行日要注意。(バス時刻は2001年11月現在) |
| 時 | 「石山駅」行 (京阪バス) |
「西教寺」行 (江若バス) |
「ケーブル坂本駅」行* (江若バス) |
| 8 | -- | 22 [48] {49} | -- |
| 9 | -- | 38 | -- |
| 10 | 39 | 15 | 06 36 |
| 11 | 39 | 00 53 | 06 38 |
| 12 | 39 | -- | 06 |
| 13 | 39 | 05 | 04 28 |
| 14 | 39 | 05 | 04 28 |
| 15 | 39 | 05 52 | 04 28 |
| 16 | 39 | 52 | 04 28 |
| (注) [48]:平日運転 {49}:土曜、日曜、祝日運転 *:9月、10月の日曜、祝日及び11月の土曜、日曜、祝日運転 |
祭神、神徳 日吉山王七社の筆頭に位置する西本宮の祭神は大己貴神(おおなむちのかみ)で、厄除け、家業繁栄、福徳開運などの神徳のある神様とされている。 東本宮の祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)で地主神であり、家内安全、土地守護、子孫繁栄などの神徳のある神様とされている。 摂社五社について:宇佐宮の祭神は田心姫神(たごりひめのかみ)、牛尾神社の祭神は大山咋神荒魂(おおやまくいのかみのあらみたま)、白山姫神社の祭神は菊理姫神(くくりひめのかみ)、樹下神社の祭神は鴨玉依姫神(かもたまよりひめのかみ)、三宮神社の祭神は鴨玉依姫神荒魂(かもたまよりひめのかみのあらみたま)。 |
由緒 |
 |
比叡山の一峰である牛尾山に神代の昔から比叡山の守護神として大山咋神が祀られていた古社に端を発し、また、大津京遷都にあたり、天智天皇7年(668年)に大和の大神神社より御神霊を迎え大己貴神を国家鎮護の神として祀ったとされているのが日吉大社の創始といわれているようである。 この二柱の大神を日吉大神と称し天皇から庶民にいたるまで広く崇敬されてきたようで、更に、約1200年前、伝教大師が比叡山に延暦寺を建立してからは、比叡山、延暦寺の鎮守として栄え、強大な影響力を持つようになったという。 日吉大社は元亀2年(1571年)に織田信長によって焼き討ちに遭ったようで、従って、現在の社殿はそれ以降に再建されたものといわれている。 |
現在、日吉神社は全国に約3800社あるといわれているが、ここ日吉大社がこれらの総本社になっている。 |
 |
鳥居 車道の脇に立っているこの朱塗りの「鳥居」(左の写真)から奥が実際上の境内になっているようであるが、駅から歩いてくるとこの鳥居までの間に二つの石造りの鳥居をくぐることになる。 従って、この鳥居は「三の鳥居」ということになるのであろう。 |
朱塗りの鳥居をくぐると、拝観料を徴収する受付がある。神社で拝観料が必要というのは珍しい。 |
 |
大宮橋 受付をすぎると西本宮への参道に、日吉三橋の中でも最も手が込んだ造りで、石造桁橋の代表的なものとされている「大宮橋」がかかっている(写真)。 この橋は天正年間(1573〜1592年)に豊臣秀吉」が寄進したものと伝えられている。 |
もとは木橋であったものが、寛文6年(1669年)に石橋に造り替えられたといわれている。 「大宮橋」は重要文化財に指定されている。 |
 |
山王鳥居 「大宮橋」を渡り、西本宮に向かって緩やかな坂を上がると「山王鳥居」が建っている(左の写真)。 写真でもわかるとおり、この鳥居は笠木の上に破風を組み中央に束があり独特の形をしている。 この「山王鳥居」は滋賀県文化財に指定されている。 |
 |
山王霊石・祇園石 西本宮の楼門前に瑞垣で囲まれた場所があり、その中にはかなり大きな石がある(左の写真)。 この石は「山王霊石・祇園石」と呼ばれているもので、祇園の神が鎮座する磐境(いわさか)とされているようである。また、この石は眼病に霊験があると伝えられている霊石であるという。 |
このような霊石はここ日吉大社に限らず、各地の神社にしばしば見られる。大きな石があれば何らかの謂われをつけて神様に結びつけている場合が多いように思われる。 |
 |
西本宮楼門 この「西本宮楼門」(左の写真)は「東本宮楼門」と同様、入母屋造り、檜皮葺であるが、こちらの楼門は「東本宮楼門」にくらべ造りは一回り大きく堂々としている。 建造されたのは天正14年(1586年)頃とされているが、正確なところはわからないという。 |
「西本宮楼門」は重要文化財に指定されている。 |
 |
西本宮拝殿 「西本宮楼門」をくぐると直ぐ前に「西本宮拝殿」が見える(左の写真)。 「西本宮拝殿」は吹きさらしの舞殿形式で、お祓い、祈祷などの神事がここで行われる他、山王祭では山王七社の神輿(後述)が全てここに安置される。 |
また、重要な仏事である山王礼拝講にも使われているようである。 「西本宮拝殿」は天正14年(1586年)に建造されたものとされており、重要文化財に指定されている。 |
 |
西本宮本殿 「西本宮拝殿」の奥に「西本宮本殿」が建っている(左の写真)。 直下の写真は「西本宮本殿」の正面部近景である。 |
 |
「西本宮本殿」と「東本宮本殿」の建築様式は共に日吉造(聖帝造)といわれ、日吉大社だけに見られる形式という。日吉造の特徴は屋根の庇が前面と両側面の三面にだけで、従って、背面の屋根は切れたような形になっているところにあるらしい。 「西本宮本殿」は日吉大社の山王七社の中で最も格が高いとされているようである。 「西本宮本殿」は天正14年(1586年)に建造されたものといわれており、国宝に指定されている。 |
 |
竹臺 「西本宮本殿」の正面に向かって左側に「竹臺」と名付けられた場所がある(左の写真)。ここには、石で囲われた狭い場所に竹が密集して植えられている。 伝教大師が中国の天台山から持ち帰った竹を植えたものと伝えられている。この竹は真っ直ぐ節目正しく生きよと教えているという。 伝教大師が中国から持ち帰った竹というのが事実であるとすれば、この竹は約1200年もの間この場所で生き続けていることになる。勿論、何代か継代されていることだろうが、見た目には実に若々しく、瑞々しい竹である。 |
 |
摂社宇佐宮本殿 西本宮本殿の東側に日吉大社の摂社「宇佐宮本殿」が建っている(左の写真)。 この宇佐宮本殿は西本宮本殿、東本宮本殿と同様に日吉造である。床下に大きな岩が露出しているというが確認は出来ないようである。 |
「宇佐宮本殿」は慶長3年(1598年)に建造されたといわれ、重要文化財に指定されている。 |
 |
山王神輿 「宇佐宮本殿」の東側に「白山宮本殿」があり、更に、山裾に沿って東の方向に進むと「神輿庫」が建てられている。 「神輿庫」の中には七基の「山王神輿(みこし)」が保存されている(左の写真はその内の一つ、白山宮の御輿)。 全国の神輿は「山王神輿」に端を発するといわれているようであるが、「山王神輿」は平安時代に桓武天皇が日吉大神に寄進したことに始まるという。 ただ、平安時代の神輿は元亀の乱で焼失したとされ、現存の御輿は何れも桃山時代の作といわれている。 |
現存の七基の「山王神輿」は全て重要文化財に指定されている。 |
 |
摂社樹下神社 「神輿庫」の前を東の方向を進むと、「東本宮楼門」が建っており、それをくぐると左手に「樹下(じゅげ)神社本殿」が見える(左の写真:正面近景)。 「樹下神社本殿」はその床下の造りが日吉造と同じであること、向拝階段前に吹寄格子の障壁が立てられている(写真参照)ことが特徴とされているようである。 |
 |
また、社殿には豪華な飾り金具などがふんだんに使われており、装飾性が極めて豊かで派手な感じのする神社である(左の写真は使われている装飾金具の一部)。 「樹下神社本殿」は文禄4年(1595年)の建築とされており、重要文化財に指定されている。 |
 |
東本宮本殿 東本宮の奥まったところに「東本宮本殿」が建てられている(左の写真)。 「西本宮本殿」の項で記述したとおり、「東本宮本殿」も日吉造の特徴を備えている。その特徴は建物の背面から見るとよくわかるとされている。 |
 |
左の写真は「東本宮本殿」の背面であり、左右の屋根を別につけたような形状になっているのがわかる。 この本殿は文禄4年(1595年)に建造されたといわれており、「西本宮本殿」の建造より9年後であるにもかかわらず、「東本宮本殿」のほうが、より古式を伝えているという。 |
これは本殿の形式が現建物の建築時に決められたものではなく、前身の建築で形式が既に決められていたことによると考えられている。 「東本宮本殿」は国宝に指定されている。 |
東本宮と樹下神社との社殿配置 「東本宮拝殿」と「東本宮本殿」は南北を結ぶ線上に位置しているが、同じ敷地にある「摂社樹下神社拝殿」と「摂社樹下神社本殿」は東西を結ぶ線上にあり、両者の延長線は交差している。このような社殿配置は珍しいが、この理由はよくわかっていないらしい。 |
亀井水 「東本宮本殿」横には「亀井水」と呼ばれている湧き水があり、年中涸れることはなく、飲用可能とされている。何人かの人がこの水を汲みに訪れてきているのを目にする。 |
 |
二宮橋 東本宮から真っ直ぐに南の方向に進むと「二宮橋」がある(左の写真)。 「二宮橋」は大宮川に架かる花崗岩製の反橋で大宮橋(上述)とほぼ同規模である。 天正年間(1573〜1592年)に豊臣秀吉の寄進によって建造されたと伝えられている。 |
「二宮橋」は日吉三橋の一つとして重要文化財に指定されている。 なお、この橋は通常は渡ることはできず、横につけられた別の橋を渡ることになっている。 |
| 名神大社二十二社一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto