| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 廣瀬神社 |
| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 廣瀬神社 |
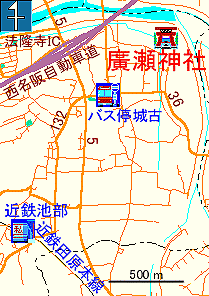 廣瀬神社へのアクセス
廣瀬神社へのアクセス近鉄田原本線「池部」駅下車。改札口を出て直ぐの踏切を渡り、道なりに北の方向に進む。西穴闇交差点を渡り、東の方向に進み、橋を渡ると神社参道の入口(廣瀬神社の標識がある)になる。駅から神社まで徒歩約25分。 近鉄池部駅前から「法隆寺駅行」の奈良交通バスが出ており、これを利用する場合は「城古」バス停で下車し東の方向へ進む。橋を渡ると神社参道の入口になる。バス停から神社まで徒歩10分弱。 池部駅から法隆寺駅行のバスは1日6便(平日、土、日曜日とも池部駅発9:08、9:51、10:50、12:50、14:51、16:09)(2000年4月現在)で便数が少なく不便である。 祭神、神徳 若宇加能売命(わかうかのめのみこと) 廣瀬神社の主神。水の守り神で河川の氾濫を防ぎ、五穀の豊穣を守る神であり、これらのことから、食物を守る御膳神(みけつかみ)とされている。 |
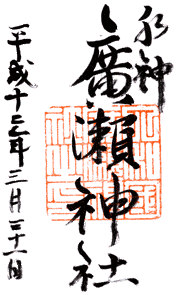 櫛玉命(くしたまのみこと)及び穂雷命(ほのいかずちのみこと) 廣瀬神社の相殿。 廣瀬神社は多くの河川が大和川に合流する地にあり、神徳は五穀豊穣、水難鎮護、河川交通安全など水に関するものが主になっているが、その他、産業振興、安産、厄除招福など数多い。 由緒、伝説 崇神天皇9年(BC89年)にこの地方の長にご神託があり、一夜のうちに沼が陸地に変わり、数多くの橘の木が生えたという。このことが天皇に伝わり、社殿が建てられたとされ、これが神社の創始であるとされている。 この地の長にご神託があったというのは、治水権を掌握していた長である地方豪族が神を祀ることにより実権を更に強固なものにするための方策であったと勘ぐることもできる。 |
 天武天皇4年(679年)に天皇が大忌祭(おおいみのまつり)を4、7月の年2回始められて以来、皇室の崇敬が厚くなったといわれている(廣瀬大社御略記)。 鳥居 写真の鳥居は拝殿の前に立っている「二の鳥居」である。写真では字が見えないが、鳥居に掲げられている「廣瀬社」の額文字はかなり変わった字体である。これは、文化4年(1807年)に大和の郡山城主が揮毫したものとされている。 |
 鳥居は朱塗りで一見派手なように見えるが、奥にある重厚で可成り地味な感じのする拝殿とよくマッチしている。 拝殿、橘 二の鳥居をくぐると広場があり、奥に「拝殿」(写真)が建っている。神社の規模からみて、拝殿は大きく立派である。 現存の拝殿は明治以降に建てられたものといわれている。 |
 拝殿の前には向かって左側に橘、右側に桜の木が植えられているのは普通で一般的であるが、廣瀬神社には拝殿前の広場にも橘の木が植えられている(左の写真)。 上述したように、ここに神社が祀られるようになった経緯からみて、たとえそれが伝説であるとしても、廣瀬神社と橘の木とは少なからぬ関係があるように思われる。 |
 本殿 「拝殿」の奥に「本殿」(左の写真)が建てられているが拝殿正面から本殿を見ることができない。 本殿をはじめ神社の建造物は永正3年(1506年)の兵火により全焼したようで、現存の「本殿」は正徳元年(1711年)に造営されたものという。 「本殿」は彩色が施され若干派手な印象を受けるが、豪壮な造りの社であり、奈良県文化財に指定されている。 なお、2000年3月末の時点で本殿は改修工事中であった。 |
| 名神大社二十二社一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto