| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 外宮 |
| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 外宮 |
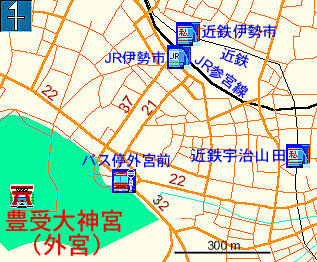 外宮へのアクセス
外宮へのアクセス近鉄山田線「伊勢市駅」又はJR参宮線「伊勢市」駅下車、駅前広場に出て西南の方向に進むと徒歩7〜8分で下宮に着く。 駅から外宮までは道路が平行に二本通っているが、車の往来の激しい広い道(県道37号線)を避け、道は細いが車の通行の少ない参道を選んだ方がよい。 近鉄山田線「宇治山田」駅で下車した場合、徒歩ではやや距離があるので三重交通バスを利用することになる。 祭神、神徳 豊受大御神(とようけおおみかみ) 天照大御神(あまてらすおおみかみ)の食事を司る神で、米をはじめ衣食住のの恵みを与える産業の守り神とされている。 |
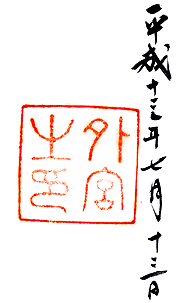 由緒 祭神の豊受大御神は今から約1500年前に丹波国から内宮の祭神天照大御神の食事を司る神様として、ここに迎えられたとされており、創始は雄略天皇(21代)22年といわれている。 現在の京都府宮津市にある「丹後一の宮籠神社」の祭神の一柱が豊受大神であり、本殿の建築様式は伊勢神宮と同じ神明造である。この籠神社は伊勢神宮元宮といわれており、伊勢神宮はここから移されたような表現になっている。これは本当なのだろうか。ここは丹波国でなく丹後国であるが・・・。 伊勢神宮の参拝は、はかつては皇室のみに許されていた特権であったが、室町時代になると将軍や武将も参拝できるようになり、次第に一般民衆も参拝可能となり、江戸時代には伊勢詣りはブームになったという。 なお、伊勢神宮の格式は最高とされ、正式には「神宮」といい、伊勢という言葉をつけないとされている。 |
 鳥居 外宮神域に入り、火除橋を渡ると「一の鳥居」が見える(左の写真)。一般に鳥居は朱塗りのものが殆どであるが、伊勢神宮の鳥居は朱に塗られていない。 鳥居の手前にある手水舎の向かい側に「清盛楠」と呼ばれている楠の大木があるらしい(2000年7月の時点では未確認)が、これは2000年12月に予定されている神楽殿の完成をまたなければ見学できないようである。 |
 正宮 「一の鳥居」、次いで「二の鳥居」をくぐると直ぐ右手に改築中(2000年7月時点)の「神楽殿」が見える。神楽殿は2000年12月に改築完成が予定されているようである。 「二の鳥居」から100m余りで外宮の中心である「正宮(しょうぐう)」の前に着く。 |
「正宮」内には「東宝殿」、「西宝殿」など数個の社殿が建てられているようであるが、直上の写真に見られるように板塀で囲われ、外からは社殿の屋根の一部や鰹木(かつおぎ:屋根の棟の上につけられた丸太状の木)、千木を辛うじて見ることができる程度である。 |
 「正宮」の板垣南御門の白い絹の帳の前が拝所になっており(左の写真)、ここから参拝するようになっているが、この場所からも「正宮」の内部を直接見ることはできない。 拝所の横から内部が見えるが、「正宮」の一番奥に位置し、祭神が鎮座する「正殿」はいくつもの垣根に遮られ、その全容を見ることができない。ここまでして一般の人々の目から社殿を隠す理由はどこにあるのだろうか。 板垣から内側での写真撮影は禁止されている。何故、写真撮影が禁止されているのかよく分からない。写真撮影は神宮の尊厳さを損なうのであろうか。 |
 亀石 正宮の前の池から出ている水路には「亀石」と呼ばれている小さな石橋(左の写真)がかかっている。 この石はよく見ると、向かって左側に頭のある亀の姿を想定させユーモラスである。 |
 土宮 亀石を渡り参道を南の方向に進むと、右手に「外宮」の別宮である「土宮(つちのみや)」が見える(左の写真)。 祭神は大土乃御祖神(おおつちのみおやのかみ)で外宮域の地主の神とされ、川の氾濫を防ぐ堤防の守護神として知られているという。 |
 風宮 亀石を渡り南の方向に進むと、左手に「外宮」の別宮である「風宮(かぜのみや)」が見える(左の写真)。 祭神は風の神、級長津彦命(しなつひこのみこと)、級長戸邊命(しなとべのみこと)で、風雨の災害を免れる農業の神として信仰されているようである。鎌倉時代の元寇の役でこの祭神が神風を起こし、元の大軍を滅ぼした功績により、末社から別宮に昇格したという。 別宮として上記の他、「土宮」の前の石段を登ったところに、外宮の第一別宮とされている「多賀宮」がある。 |
 勾玉池と奉納舞台 一の鳥居をくぐらずに左手に進むと、「勾玉池」に出る。池には「奉納舞台」が設けられ(左の写真)、花菖蒲が植えられている。 池は勾玉の形をしているので勾玉池と呼ばれているようで、6月には花菖蒲が花をつけ、秋にはこの舞台で観月会が催されるようである。 |
| 名神大社二十二社一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto