| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 伏見稲荷大社 |
| ホーム > 名神大社二十二社一覧 > 伏見稲荷大社 |
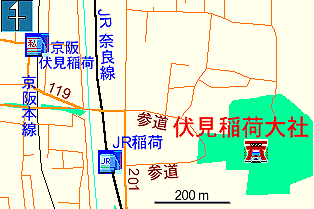 大社へのアクセス
大社へのアクセス京阪電車「伏見稲荷」駅(急行停車)下車、JRの踏切を渡り東の方向に進むと伏見稲荷大社への参道(御幸道)がある。駅から大社まで徒歩約5分。 JR奈良線「稲荷」駅下車、道路を隔てて第一鳥居の建っているのが見える。鳥居をくぐり表参道を東の方向に進むと大社に着く。駅から大社まで徒歩2〜3分。 電車の便数からみて、JRよりも京阪を利用する方が便利である。 祭神、神徳 宇迦之御魂大神(うがのみたまのおおかみ) 伏見稲荷大社の主神。中央座に祀られている。 |
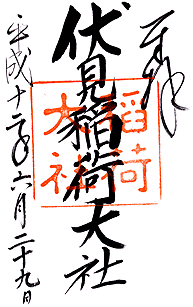 佐田彦大神(さたひこのおおかみ)、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)、田中大神(たなかのおおかみ)、四大神(しのおおかみ) 以上五柱の祭神名は稲荷大神の広大な神徳の神名化されたものという。 平安時代の昔から稲荷山が民衆信仰の山であったことに始まり、今日では商売繁盛、産業興隆、家内安全、交通安全、芸能上達の守護神として信仰をあつめている。 由緒、伝説 深草の長者であり、当時栄えていた秦伊呂具はおごり高ぶり、餅を的に矢を射たところ、餅は白鳥となり伊奈利(稲荷)三ヶ峰の方角に飛び去った。これを機に、秦氏に衰えが見えはじめたため、秦伊呂具は和銅4年(711年)に伊奈利(稲荷)三ヶ峰に神を祀った。これが大社の創始と伝えられている。 社殿が現在の地に移されたのは弘仁7年(816年)とされているようである。仁寿2年(852年)に降雨祈願の奉幣が行われて以来、朝廷からたびたびの勅使が遣わされ信仰をあつめたという。 |
 第一鳥居 JR稲荷駅を出ると正面に大きな「第一鳥居」の建っているのが見える(左の写真)。こちらの参道が表参道になっているようである。京阪伏見稲荷駅から御幸道を通って大社を訪れた際はこの鳥居をくぐらない。 「第一鳥居」をくぐって参道を東に進むと、「第二鳥居」の建っているのが見える。 |
 楼門 第二鳥居をくぐるとその奥に規模の大きな朱塗りの「楼門」が建っている(左の写真)。 以前の楼門は応仁の乱により焼失し、現存のものは再建に尽力した秀吉の寄進によるものらしい。 一般に神社は年中行事としての祭事が多いが、伏見稲荷大社もその例にもれない。6月にここを訪れたとき、6月30日の水無月大祓式の神事用の茅輪が楼門中央の通路に置かれており、参拝者は輪の中をくぐって通るようになっていた。 |
 狐の狛犬 「楼門」の前や「本殿」の前などには普通、阿吽の狛犬が置かれているが、伏見稲荷大社の場合、狛犬に代えて狐の像が置かれている。 左の写真は「楼門」の前左側の狐の像であるが、このような像が「本殿」(後述)の前は言うに及ばず、その他諸所に置かれている。また例えば、稲荷山中にある眼力社の手水場の水も狐の像の口から出ているなど、狐の像がふんだんに使われている。 「稲荷」という名称は「稲生(いねなり)」に基づいているとされ、もともとは農業の神であったといわれており、「稲荷」と狐とは結びつかないのである。狐と稲荷大社との間にどのような関係があるのだろうか。 |
 拝殿及び本殿 「楼門」の奥には「外拝殿」が建っており、「外拝殿」の奥に「内拝殿(神饌所)」(左の写真)及び「本殿」が建てられている。 写真は「内拝殿(神饌所)」の正面(西側)である。この奥に「本殿」があり、この場所から「本殿」を参拝するようになっている。 この「内拝殿」は昭和の建築らしい(未確認)。 |
 左の写真は北側から見た「本殿」である。内拝殿は向かって右側(本殿の正面)に付けられており、本殿の屋根が拝殿側に伸びているのが特徴的である。この建築様式を稲荷造というようである。 以前の「本殿」は応仁の乱で焼失し、現存の建物は明応8年(1499年)に再建されたものとされており、更に、最近一部追加建築されたようである。 「本殿」は重要文化財に指定されている。 |
 稲荷山御神蹟参拝 「本殿」の左手奥側に本殿造営の時に祭神を一時移し祀る「権殿(かりどの)」が建っており、「権殿」の横から稲荷山の方へ登る石段がある。 この石段を上ると「稲荷山御神蹟参拝」(一般には「お山めぐり」とも呼ばれているようである)の始まりになる。 由緒の項にも述べたとおり、大社後方の稲荷山は伏見稲荷大社創始の霊地として今も崇敬をあつめており、稲荷山中に祀られている数多くの社、神蹟をめぐり、お詣りする御神蹟参拝者は多い。 千本鳥居 |
 稲荷山御神蹟参拝の参道の殆どは直上及び左の写真に見られるように朱塗りの鳥居がビッシリと建てられており、まるで鳥居のトンネルをくぐるような状態で参道を歩く。 これを「千本鳥居」と呼んでいるようであるが、実際は数千本の鳥居が建てられているという。 御神蹟参拝参道を少し上がったところに「奥社奉拝所」がある。 |
 おもかる石 「奥社奉拝所」の傍に「おもかる石」という奇妙な名前の書かれた場所がある(左の写真)。 ここにある石灯籠の前で願い事をし、燈籠の空輪(頭の丸い石)を持ち上げる。持ち上げたときに感じる重さが予想より軽ければ願い事が叶い、重ければ叶わないといわれている。 御神蹟参拝参道を更に進む 「奥社奉拝所」から更に御神蹟参拝参道を上がり、途中「熊鷹社」など参拝し、「四つ辻」までは登りのほぼ一本道である。 「四つ辻」からは左回りで参拝する方法と、右回りで参拝する方法がある。参道は循環しているからどちら回りで参拝しても「四つ辻」に戻ってくる。 |
 一の峰上社神蹟 稲荷山山頂には「一の峰上社神蹟」があり(左の写真)、一の峰御神蹟の霊地とされている。 「一の峰上社」の拝所はこぢんまりした簡素な建物で、拝所の奥には注連縄(しめなわ)を懸けたかなり大きな石が安置されているのを見ることができる(直下の写真)。この石が「ご神体」と思われる。 ここは御神蹟参拝の参道で最も高度の高い場所である。 |
 その他の社、神蹟 「一の峰」から一寸下がった場所に「二の峰中社神蹟」、更にその下に「三の峰下社神蹟」があり、何れも社、ご神体共に「一の峰上社神蹟」に類似している。 その他に、「眼力社」、「御膳谷奉拝所」、「薬力社」、「剣石」など、数多くの社、神蹟がある。 「本殿」横から出発し、稲荷山御神蹟参拝参道を通り、「本殿」まで戻ってくるには、主要な社の参拝時間も含め約2時間を要する。急勾配の坂もありかなり厳しい。 |
 奉納小鳥居 稲荷山の神蹟や社には、住所氏名を書いた高さ数十センチの朱塗りの鳥居が数多く奉納されている。 左の写真は奉納された鳥居のごく一部であるが、稲荷山に奉納されているその総数は莫大なものである。 伏見稲荷大社にたいする一般の信仰の深さは「千本鳥居」や奉納された小鳥居の数にも表れているが、これだけ多くの人からそれぞれ願い事をされると、これをさばく神様も大変なことであろう。 |
| 名神大社二十二社一覧のページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto