| ホーム > 関西花の寺めぐり > 般若寺 |
| ホーム > 関西花の寺めぐり > 般若寺 |
| 所在地及びアクセス: 奈良市般若寺町 |
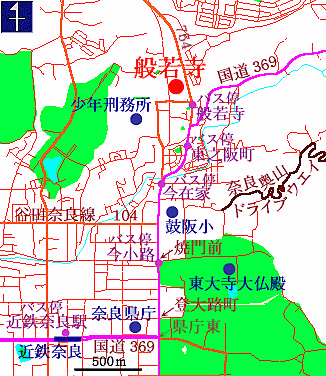 近鉄「奈良」駅下車。地上に上がり国道369号線(登大路)北側にある奈良交通バス停「近鉄奈良駅」(2番のりば)より「青山住宅」行きバスに乗車し、「般若寺」で下車する。バス停の直ぐ北側にある道路を西の方向に進む。約150m進んだ後、右折し北の方向に数10m進むと右手に般若寺の入り口がある。バス停から般若寺まで徒歩数分。 なお、「青山住宅」行きバスはJR「奈良」駅から出ているので、奈良交通バス停「JR奈良駅」からバスに乗車してもよい。 |
「青山住宅」行き奈良交通バスの「近鉄奈良駅」発車時刻は8時〜18時の間について下表の通りである(2003年1月現在)。 |
| 時 | 平 日 | 土 曜 日 | 日曜日・祝日 |
| 08 | 09 18 24 31 39 49 55 | 04 13 23 33 40 48 57 | 03 13 25 35 44 57 |
| 09 | 01 09 15 24 36 47 57 | 09 21 33 41 49 57 | 09 21 33 41 49 57 |
| 10 | 09 21 33 45 57 | 10 21 33 45 57 | 09 21 33 45 57 |
| 11 | 10 22 34 46 58 | 10 22 34 46 58 | 10 22 34 46 58 |
| 12 | 10 22 34 46 58 | 10 22 34 46 58 | 10 22 34 46 58 |
| 13 | 10 22 34 46 58 | 10 22 34 46 58 | 10 22 34 46 58 |
| 14 | 10 22 34 46 58 | 10 22 34 46 58 | 10 22 34 46 58 |
| 15 | 10 22 35 46 54 59 | 10 22 35 43 54 59 | 10 22 35 43 54 59 |
| 16 | 09 19 26 35 44 59 | 08 19 26 36 44 59 | 08 19 26 36 44 56 |
| 17 | 04 14 21 29 38 45 50 58 | 10 19 28 38 48 59 | 10 19 28 38 48 59 |
縁起: |
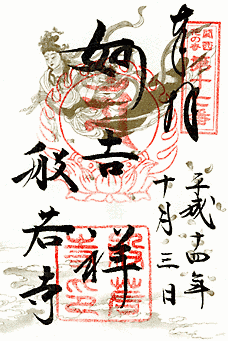 |
この寺は飛鳥時代に高句麗の僧である慧灌(えかん)法師によって開創されたと伝えられている。その後、天平18年(746年)には聖武天皇が平城京の繁栄と平和を願い卒塔婆を建て鬼門鎮護の定額寺に定めたといわれている。 その後、寛平7年(895年)頃には観賢僧正が学問道場の礎を当寺に築いたこともあり、以来、般若寺の名声は広く知れ渡り大いに栄えたようであるが、治承4年(1180年)に平重衡の戦火に遭い、全て灰燼に帰したという。 鎌倉時代に入り復興を遂げたが、室町戦国時代には戦乱により衰退、江戸時代になり再び復興したようであるが、明治の廃仏毀釈により一時期廃寺になったという。その後復旧し、現在は「花の寺」、「コスモス寺」ともよばれ、季節には多くの観光客、参拝客で賑わっている。 |
当寺の花: |
1.主たる花: コスモス(右の写真) 見頃は9月下旬〜11月上旬 2.その他四季の花 春:山吹(4月) 夏:あじさい(6〜7月) 冬:山茶花、水仙 |
 |
当寺の通称:花の寺、コスモス寺 |
見所など: |
 |
般若寺につくと、先ず道路の右手に「楼門」(左の写真)の建っているのが見える。写真でわかるように、この「楼門」を通して奥に「十三重石宝塔」(後述)を望むことができる。 この「楼門」は一見してもわかるが、非常に均整のとれた形をしており、楼門建築の傑作といわれている。 本来ならばこの門から境内に入るのであろうが、現在、柵が設けられており門をくぐることはできない。境内への入り口はこの楼門の前を通り少し北側に歩いた場所にある。 |
 |
上述の通り表側(道路側)から「楼門」に近づくことはできないが、境内からは近くに寄ることができる。 境内から「楼門」までの間には狭い通路がつけられており、その両側はコスモス畑になっている(左の写真)。 この「楼門」は国宝に指定されている。 |
 |
「本堂」(左の写真)は境内で最も大きな建物で、正面や側面にはコスモス畑が迫っている。 現存の「本堂」は寛文7年(1667年)に建立されたものというが、見た目には古色蒼然という感じはしないので、建立後、何回か解体修理が行われているものと推測される。 |
 |
左の写真は「本堂」を南東側、十三重石宝塔の近くから見たものである。 この付近に植えられているコスモスの草丈はかなり高いので、花の最盛期には「本堂」は屋根の部分が見えるだけになる。 「本堂」は奈良県指定文化財である。 |
 |
左の写真はコスモス畑を通して見た「本堂」の正面である。 かつて、「本堂」には文永4年(1267年)に造られた文殊菩薩丈六像が本尊として祀られていたというが、延徳2年(1490年)の火災で本堂と共に焼失してしまったようである。 本堂の東南側、十三重石宝塔の東側にある「経蔵」は、この火災や兵火からも免れたが、「経蔵」には元享4年(1324年)に仏師康俊、康成によって造られたとされている「文殊菩薩騎獅像」が秘仏として祀られていたといわれている。「本堂」が再建されたとき、この「文殊菩薩騎獅像」が「経蔵」から移され、以後、「本堂」の本尊として祀らるようになったという。 本尊「文殊菩薩騎獅像」は重要文化財に指定されている。 |
 |
「本堂」の前にかなり大きな「石灯籠」(左の写真)がある。 この灯籠は鎌倉時代後期の作と伝えられており、般若寺型と称されているという。 |
 |
「楼門」の東側で「本堂」の東南の位置にそびえ立っているのが「十三重石宝塔」であり、般若寺の伽藍の中心でシンボル的存在であり、境内で最も目を引く建造物である。左の写真はやや南寄りの東(東南東)側から見た「十三重石宝塔」である。 「十三重石宝塔」は聖武天皇の創建になるものと伝えられている。現存の塔は建長5年(1253年)頃、南宋の石工、伊行末によって建てられたとされている。 塔は花崗岩で作られており、その高さは約14m、重さは約80トンといわれている。石塔としては日本の代表的なものとされているだけあり、近くから見上げるとその規模と造りに圧倒される。 石塔の四方には、東に薬師、西に阿弥陀、南に釈迦、北に弥勒の各如来が配されている。 |
 |
この石塔は昭和39年(1954年)に解体修理が行われたようで、この時、水晶五輪塔、金銅舎利塔、銅造如来立像などが取り出されたという。これらの秘宝秘仏類は春と秋の特別寺宝展で公開されているようである。 左の写真はやや北寄りの西(西北西)側から見た「十三重石宝塔」である。見るからに歴史のある石塔にコスモスがよく映えている。 「十三重石宝塔」及びそこから取り出された水晶五輪塔、金銅舎利塔、銅造如来立像などの秘宝秘仏類は重要文化財に指定されている。 |
 |
「本堂」の東側に二基の「笠塔婆」が建っている(左の写真)。 この塔は「十三重石宝塔」を建てた伊行末の息子である行吉が父の追善供養と母の無病息災を願って弘長元年(1261年)に建立したものといわれている。 塔の高さは4.8mといわれており、彫られている梵字は北塔(向かって左側)は阿弥陀三尊、南塔(向かって右側)は釈迦三尊であるという。 この二基の「笠塔婆」は重要文化財に指定されている。 |
 |
境内には左の写真にあるような「観音石像」が多数見られる。 これらは、西国三十三ヶ所霊場観音を模して造られた石像で、山城国の寺島氏が病気平癒の礼と体の不都合で三十三ヶ所巡礼のできない人のために、元禄16年(1703年)に寄進造立したものといわれている。 |
 |
境内には参詣のための通路がついているが、コスモスの花の最盛期には通路の方にまで被さってきた状態になるほど花が咲き乱れ(左の写真)、さすがにコスモス寺といわれるだけのことはある。 ただ、一寸時期を外すと花が少なく貧弱になり、コスモス畑の中に生えている雑草が目立ち興醒めとなるので、花の寺詣でとしては時期を選んで参詣したい。 |
| 関西花の寺めぐりのページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto