| ホーム > 関西花の寺めぐり > 岩船寺 |
| ホーム > 関西花の寺めぐり > 岩船寺 |
| 所在地及びアクセス: 京都府木津川市加茂町岩船上ノ門 |
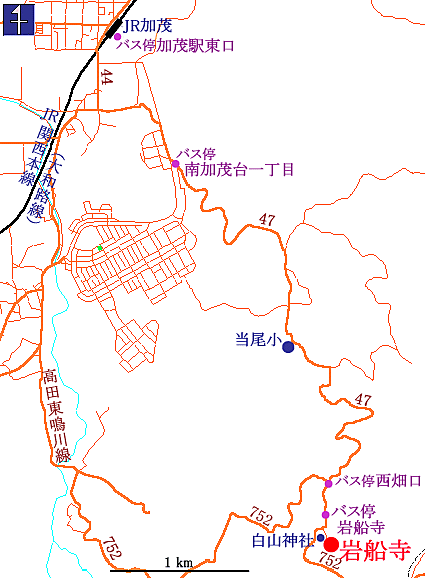 JR関西本線(大和路線)「加茂」駅下車。駅の東側に出るとバス停「加茂駅東口」があるので、そこからエヌシーバス系統番号10「加茂山の家(岩船寺経由)」行きに乗車し「岩船寺」で下車する。バス乗車時間は約15分間。 バス停から徒歩数分で岩船寺山門に着く。 他に、JR奈良駅及び近鉄奈良駅より奈良交通バス系統番号105「広岡」行き又は96「下狭川」行きに乗車し「岩船寺口」で下車する。バス停から岩船寺まで徒歩約25分。(このコースは左の地図には記入されていない) エヌシーバスの便数は下記に示すとおり少ないが、JR奈良駅及び近鉄奈良駅から出る奈良交通バスの便数も殆ど同じで少なく、徒歩時間を考慮すれば、加茂駅東口から出るエヌシーバスの方が便利である。 |
系統番号10「加茂山の家」行きエヌシーバスの「加茂駅東口」発車時刻は次の通り(2008年10月現在)。 |
| 時 | 系統[10]「加茂山の家」行き | |
| 平日 | 土曜日、日祝日 | |
| 09 | 18 | 15 |
| 10 | -- | 15 |
| 11 | 59 | 15* |
| 12 | -- | -- |
| 13 | -- | 15 |
| 14 | 59 | 15* |
| 15 | -- | 15 |
| 16 | 15 | 35 |
| 17 | -- | -- |
| 18 | 22 | -- |
| (注)* 4月1日〜6月30日及び9月第2土曜日〜11月23日の間運行 |
「岩船寺」から「加茂駅」行きのエヌシーバス発車時刻は9時以降について次の通り(2008年10月現在)。 |
| 時 | 系統[10]「加茂駅」行き | |
| 平日 | 土曜日、日祝日 | |
| 09 | -- | 54 |
| 10 | 11 | 54 |
| 11 | -- | 54* |
| 12 | 51 | -- |
| 13 | -- | 54 |
| 14 | -- | 54* |
| 15 | 46 | -- |
| 16 | -- | 04 |
| 17 | 08 | 24 |
| (注)* 4月1日〜6月30日及び9月第2土曜日〜11月23日の間運行 |
縁起: |
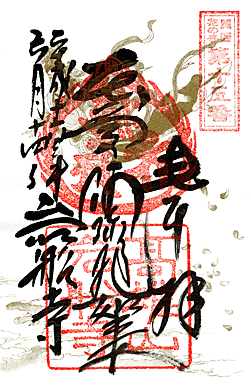 |
天平元年(729年)に聖武天皇の勅願により、行基に命じこの地に阿弥陀堂を建てさせたのが当寺の創建と伝えられている。但し、後述するように創建されたのは10世紀半ばとする説もある。 大同元年(806年)には空海と姉の子の智泉が新たに報恩寺を建立したとされており、嵯峨天皇が皇子の誕生を祈って効があったといわれている。この皇子が後の仁明天皇である。そのこともあって、弘仁4年(813年)に堂塔伽藍が建立整備され、岩船寺と称するようになったという。 最盛時には三十九もの坊があったとされているが、承久3年(1221年)の戦火(承久の乱)により殆ど焼失したといわれている。その後、江戸時代には最盛時には及ばないものの堂宇が十棟程度になるまでに復興されたようである。 |
当寺の花: |
1.主たる花 紫陽花(アジサイ)(右の写真) 見頃は6月中旬〜7月上旬 2.その他四季の花 春:つつじ 夏:睡蓮 秋:紅葉 |
 |
見所など: |
 |
岩船寺の山門前石段の手前右側に巨岩をくり抜いて作られた「石風呂」(左の写真)が置かれている。 この「石風呂」は鎌倉時代の作とされているようで、当時、岩船寺の最盛期三十九坊の僧がこれで身を清め岩船寺へお参りしたという。 |
 |
短い石段を上がると岩船寺の「山門」(左の写真)がある。山門は小ぶりであるが、この寺の佇まいによく調和している。 |
 |
「山門」をくぐると季節には両側に紫陽花の花の咲いている参道があり、そこから奥の木立の間にある「三重塔」を望むことができる(左の写真)。 |
 |
「三重塔」が正面に見える一寸した広場の右手(西側)に「本堂」(左の写真:南側から遠望した本堂)が建てられている。 戦火により焼失した本堂は江戸時代、寛永の頃に再建されたというが、それも老朽化に耐えられず、現存の「本堂」は昭和63年(1988年)に落成したものといわれている。 |
 |
「本堂」(左の写真)の中には本尊の阿弥陀如来座像が、その脇に、鎌倉時代の作とされる四天王立像が安置されている。 本尊は高さ約2m85cm、ケヤキの一本造りで胎内に天慶9年(946年)制作の銘が書かれているという。作者は行基と伝えられている。何回か修復されていると思われるが、状態は非常に良好である。この本尊の銘から、当寺の創建を10世紀半ばとする説もある。 |
この他に、普賢菩薩騎象像など、数多くの仏像が「本堂」に安置保管されている。本尊を含めこれらは全て公開され拝観可能である。 本尊の「阿弥陀如来座像」、「普賢菩薩騎象像」は重要文化財に指定されている。 |
 |
「本堂」前の一寸した広場の東側やや奥まったところに石室があり、その花崗岩の奥壁に、薄肉彫りの「石室不動明王立像」(左の写真)がある。 石室には応長2年(1312年)願主盛現の銘があるという。岩船寺の塔頭湯屋坊の住僧、盛現は眼病を患い悩まされていたが、不動明王に七日間の断食修行を行ったところ、満願日に眼病は治癒と伝えられている。この恩に報いるため自らこの不動明王を彫ったといわれている。 この不動明王立像は経年により風化をうけて不明瞭になってはいるが、不動明王らしいことは理解できる。 「石室不動明王立像」は重要文化財に指定されている。 |
 |
「石室不動明王立像」近くの北側に「五輪石塔」(左の写真)が建てられている。 この石塔は鎌倉時代の作といわれているが、建立の謂われなどはわからないようである。 この「五輪石塔」は重要文化財に指定されている。 |
 |
「本堂」前の一寸した広場の南東隅から三重塔の方角に進む参道の傍に「十三重石塔」(左の写真)が建てられている。 この石塔は正和3年(1314年)に妙空僧正が造立したものと伝えられ、軸石のくぼみの中から水晶の五輪舎利塔が見つかったという。 「十三重石塔」は重要文化財に指定されている。 |
 |
「本堂」の直ぐ南側に小さな池があり、夏には睡蓮の花が咲く(左の写真)。 |
 |
「本堂」の前から南側に「三重塔」(左の写真)を見ることができる。 「本堂」前の一寸した広場の隅には紫陽花が植えられており季節になると花が咲く。この紫陽花の花を通して見た「三重塔」は絵になるようで、多くのカメラマンが集まる。カメラの前を通ると文句を言うカメラマンが時々いるが、参拝者にとってカメラマンは迷惑になることもあるので心してほしいものである。基本的に三脚の使用は止める方向で検討すべきであろう。 |
 |
「三重塔」(左の写真)は境内突き当たりの台地の上に建てられている。 承和年間(834〜847年)に仁明天皇が智泉大徳の遺徳を偲んで宝塔をを建立したのが最初であると伝えられており、後、鎌倉時代に再建されたといわれている。現存する塔には室町時代の嘉吉2年(1442年)の銘があるといわれており、その後再建されたものであろうか。 現存の塔は見た目に非常にきれいで新しく、最近大修理されたようである。これで、創建当時の色彩を取り戻したといわれているが・・・。 「三重塔」の須弥壇後方の来迎壁は極彩色の真言八祖像といわれているが、通常は拝観できない。 |
「三重塔」は重要文化財に指定されている。 |
 |
左の写真のほぼ中央に見えるのが「天邪鬼(あまのじゃく)」である。 「天邪鬼」は「三重塔」の隅垂木を支えている木彫りであり、ユーモラスな風貌をした人(鬼)に似せて作られている。 この「天邪鬼」も重要文化財に指定されている。 |
 |
「三重塔」の周辺にも紫陽花が植えられており、左の写真見られるように赤く彩色された三重塔をバックに紫陽花を撮影することができ、ここも多くのカメラマンが撮影の対象にしているようである。 |
 |
「三重塔」の東側やや小高い場所に「鐘楼」が建っているが、「三重塔」の近くから「鐘楼」付近更に南側の斜面に沿って多くの紫陽花が植えられている。 左の写真は鐘楼傍の紫陽花である。 |
 |
「本堂」の南側の池の傍に「身代地蔵菩薩」(左の写真)がある。 この地蔵は土中から掘り出されたもので、罪深い衆生を仏道に導くために、成仏されることなく衆生の苦しみを自ら受けられる地蔵という。 |
 |
「三重塔」の裏手から寺の後方にある貝吹山の山頂に上がると大きな一枚岩の「貝吹岩」(左の写真)がある。 かつて周辺にあったとされる三十九坊の僧を集めるためにこの岩に上ってホラ貝を吹いた場所と伝えられているが、一方、念仏行者が目想観を行った場所ともいわれている。 ここは伽藍からかなり離れた場所であるため参詣者は殆ど訪れないようである。 |
岩船寺の境内で見た紫陽花のうち、4枚の花の写真を以下に示す。 |
 |
これは西洋紫陽花から改良された品種で、「ブルーリング」といわれるものと思われる。 |
 |
淡緑色の紫陽花、これはノリウツギの品種「ミナヅキ」と思われる。ノリウツギは日本の自生種とされている。 |
 |
「ガクアジサイ」の品種と思われる。ガクアジサイやヤマアジサイは変異が多く、多彩である。 |
 |
ガクアジサイかヤマアジサイか明確ではないが、形、色は「日向ヤマアジサイ」に似ている。 |
2004年7月6日新規収載 |
| 関西花の寺めぐりのページへ戻る | このページの先頭へ戻る |
Yukiyoshi Morimoto